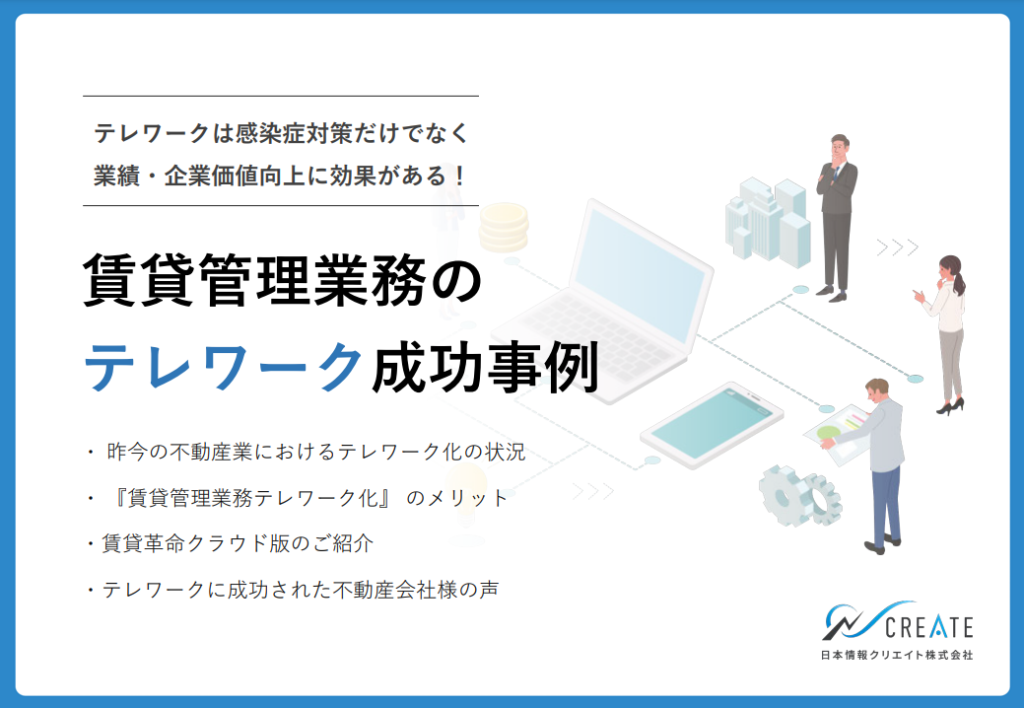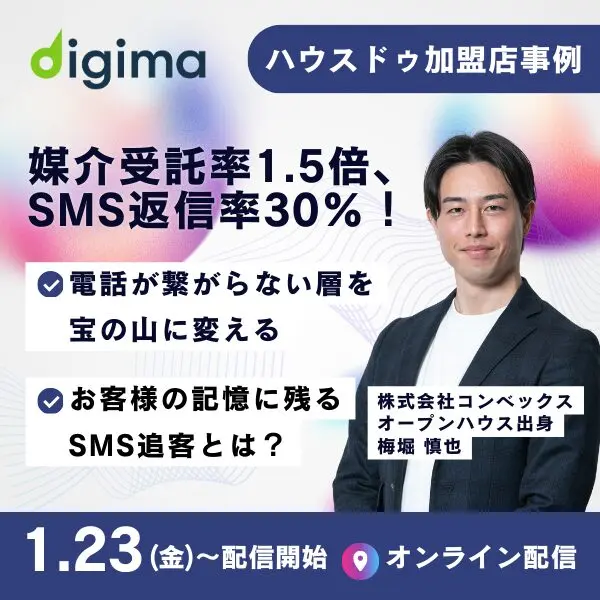不動産業界において、KPIという言葉が使われはじめて久しい。
これまで多くの現場では、仲介業なら「反響件数」「来店件数」「成約件数」、管理業なら「入居率」「退去率」「管理戸数」といった、いわば件数主義の指標が主流だった。
(実際に自分自身もこうした指標をクライアントに設定することが多かった。)
当然のことだが、数字が出るものを追う。成果が見えるものを重視する。
それ自体は間違ってはいないだろう。
しかし、この数年で世の中、特に不動産業界は大きく変わった。
こうした変化に対応するために、KPIの再定義が必要なフェーズに突入していると感じる。
実際の背景として業界構造とユーザー行動の変化があるだろう。
かつては物件情報が限られていた時代、仲介会社が情報の「ハブ」であった。
しかし今は、ポータルサイトやSNSを通じてユーザー自身が情報収集をし、複数社へ同時に問い合わせを行うのが当たり前になっている。
要はユーザーの意思決定プロセスが高度化・分散化しているということだ。
もはや「反響数」や「来店件数」だけを追っていては、本質的な成果は掴めにくくなっている。
成約までのプロセスを分解し、どこにボトルネックがあるのか、どこで価値提供ができているのか、を細かく測る指標が求められている。
そこで今回は、賃貸仲介業、賃貸管理業の新しいKPI指標をいくつか紹介してみたい。
実際、KPIを変更することによって成果を伸ばした会社も多く存在しているので、是非参考にしてみてほしい。
まず、賃貸仲介業のKPIについて紹介したい。
かつての仲介は「とにかく件数をこなす」営業が強かった。
だが今は、そのやり方では限界がある。
来店数を増やすために無理な追客を繰り返し、紹介できる物件が他社と同じではユーザーは動かなくなった。
さらに、ネットやチャットでの問合せが増えたことで、「来店=勝負の場」ではなくなった。
すでに来店時にはユーザーは十分な情報を持っている。
だからこそ、成約単価やコンバージョン率といった「質」の指標が重要になってきているように感じる。
とある会社では、1件あたりの粗利や成約までの接点数、またLINEやメールチャットでの反響対応から成約までの転換率といった、新しいチャネルに対応したKPIを設定していた。
実際にこうした指標は、営業の「対応力」や「戦略性」を測ることができ、導入した会社では有効に働いていた。
他には、顧客の満足度やNPSといった、再来店や紹介につながる「未来の売上」を意識したKPIを取り入れる企業も増えてきている。
目の前の数字だけではなく、時間軸を「長く」捉えるイメージだ。
短期的な契約数だけでなく、中長期的なユーザーとの関係の質を評価する視点が不可欠になっている。
また、仲介現場では属人的な営業スタイルから脱却し、「チームとしての成果」を見える化する動きも始まっている。
担当者別の成約件数だけではなく、対応スピード、提案件数、反響対応の初動率など、営業プロセスを分解したKPIによって、個々の動きがチーム全体にどのように影響しているのかを把握することが可能になる。
これは人材育成や業務効率の改善にも直結している。
こうしたチームとしての成果をKPIに設定している仲介会社は、総じてスタッフのモチベーションも高く、離職率も低い印象だ。
次に、賃貸管理業のKPIについて紹介したい。
管理業務は一般的に裏方的で、数字にしづらい業務が多い。
だからこそ、KPIが単純化しやすく、「入居率」や「退去率」に偏ってしまう傾向がある印象だ。
とはいえ、空室が埋まっていても利益が出ていない、あるいは人手が足りず対応が滞っている、という現象は少なくない。
これを防ぐために、「結果」だけでなく「プロセス」を測るKPIを導入する管理会社も増えてきた。
具体的には、空室の平均募集期間、退去から次の入居までの期間、原状回復やクリーニング手配のスピード、問い合わせ対応までの時間など、日々の業務を「見える化」する指標である。
他には、1戸あたりの管理利益を明確にし、業務量に対して収益が見合っているかどうかを測る視点も欠かせない。
今後、業務のDX化が進むなかで、RPAやクラウドツールを使った業務効率の改善が進む。
すると、KPIとして「業務自動化率」や「人力対応比率」といった新しい指標も設定されるようになるかもしれない。
また、オーナーとの関係性を数値化する視点も求められるようになってきている。
たとえばオーナー満足度の調査スコア、継続契約率、追加管理物件の依頼件数など、単なる管理戸数では測れない「信頼と期待」の深さをKPI化することで、担当者の成果がより適切に評価されるようになるだろう。
入居者についても同様で、クレーム対応の初動時間や解決率など、定性的になりがちな対応業務を数値として蓄積し、組織的に改善を図る動きが進んでいくことが予想される。
以上のように仲介・管理それぞれにおいて、従来の単純な件数指標ではもはや現場の実態を捉えきれなくなっている。
実際に以前のKPIだとなかなか現場の状況は見えずらくなっており、私自身も多くの会社で経営陣と営業メンバーでの軋轢を目にする機会が増えてきている。
KPIを見直すということは、評価の視点を変えることであり、行動を変えることであり、組織文化そのものを変革することに直結する。
KPIは単なる業績評価ツールではないのだ。
是非改めて自社のKPI指標を見直してみても良いかもしれない。