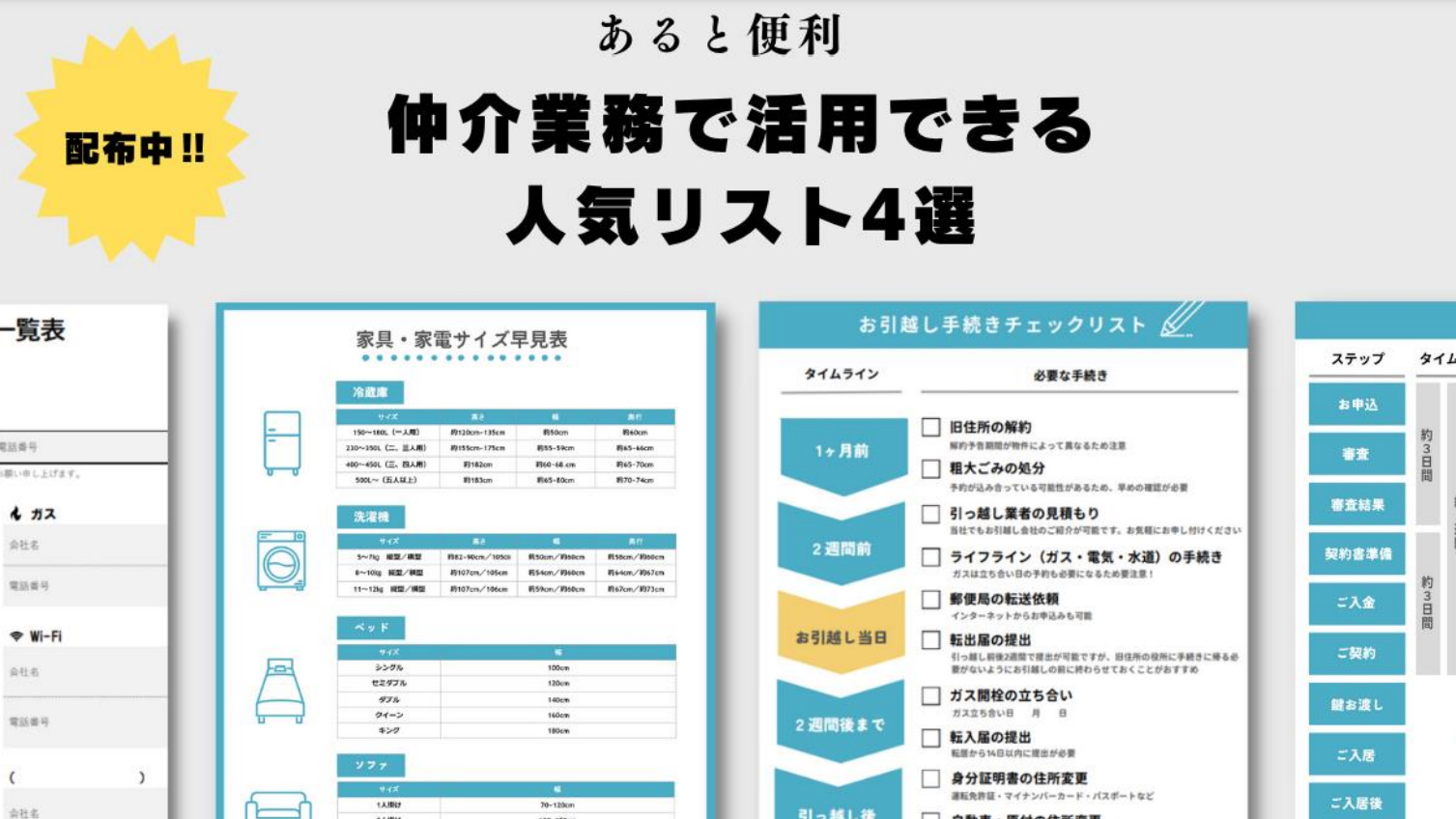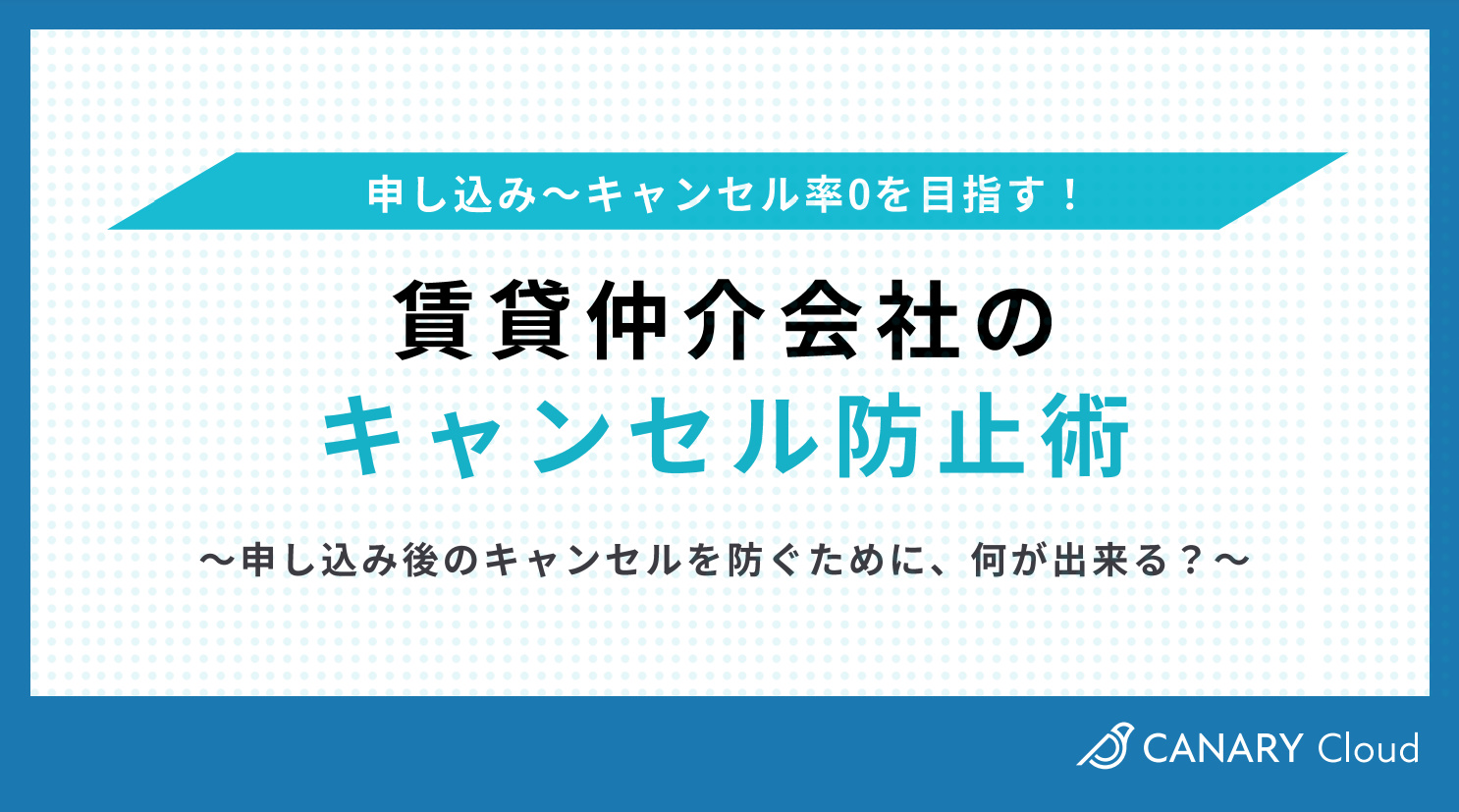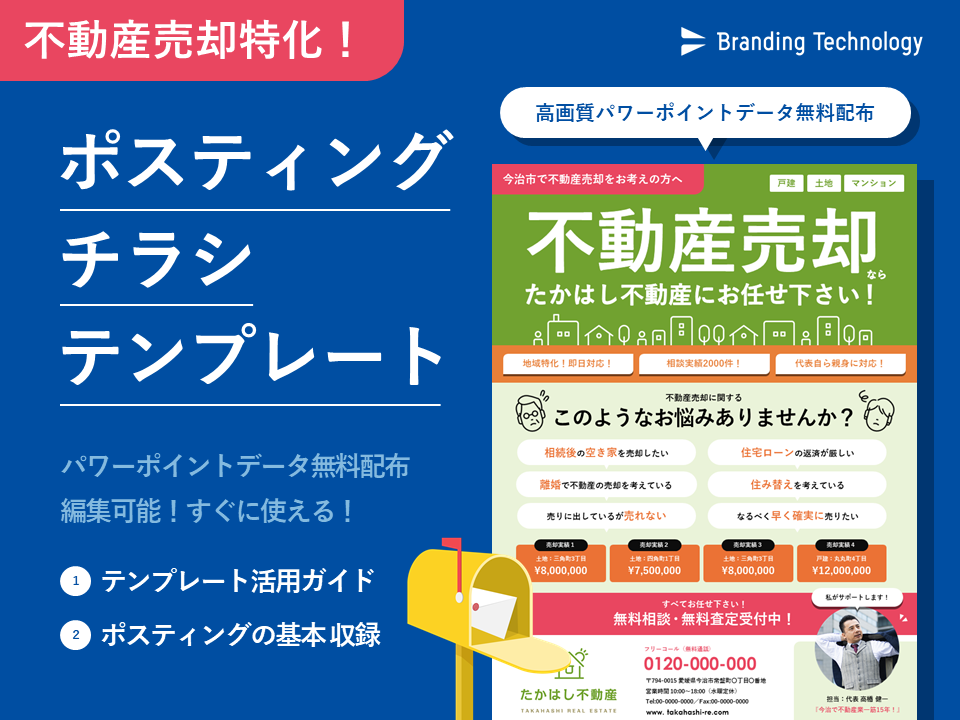賃貸仲介業において、反響返信率が高い店舗にはいくつかの共通する特徴がある。
それらの店舗は、単に問い合わせに対して返信をするだけではなく、返信の「質」と「スピード」の両面で優れており、その対応力が顧客の信頼を得て、結果として返信率の向上につながっている。
実際のところ、返信率に対して悩んでいる仲介店舗は驚く程多い。
なかなか来店が取れない営業メンバーの口癖の「会うことができれば、申込は取ることができる」というセリフがまさにそれを指している。
残念ながら、なかなか返信率は「営業テクニック」だけでは改善できない。
逆に営業スキルがそこまで高くなくても、返信率の高い店舗は存在している。
そこで今回は返信率の高い仲介店舗の特徴を紹介してみたい。
まず大きな特徴として挙げられるのが、自動返信システムの導入だ。
これは問い合わせを受けた直後に自動的に返信を送信する仕組みであり、ユーザー側から見れば「問い合わせが確かに届いた」という安心感につながる。
特に物件の問い合わせは一人のユーザーが複数の不動産業者に同時に連絡をするケースが多いため、返信の早さがそのまま「この店舗に相談してみよう」という心理的な優位性につながる。
手動での返信を待つよりもはるかに効率的かつ効果的であり、このシステムを導入している店舗では、そうでない店舗と比べて明らかに初動対応の質が高い。
今や多くの仲介店舗で導入が進んでいると思うが、まだ未導入の店舗は積極的に導入を考えてみても良いかもしれない。
しかし、いくら返信が早くても不十分である。
なぜなら返信内容の「的確さ」も同様に重要となるからだ。
ここで鍵を握るのが、多くの返信テンプレートをあらかじめ用意しておくという対応だ。
テンプレートはただの定型文ではなく、様々な問い合わせ内容やユーザーの属性に応じて使い分けが可能なよう、細かく設計されている必要がある。
たとえば、ファミリー向けの物件を探しているユーザーと、学生や単身者向けの物件を探しているユーザーとでは、同じ内容の返信では響かない。
返信テンプレートを複数用意しておけば、そうした顧客ごとのニーズに即した対応ができ、より深いコミュニケーションを築くことが可能になる。
また、テンプレートの効果を最大限に引き出すためには、顧客を適切にカテゴライズし、返信内容をパーソナライズする工夫が欠かせない。
単純な年齢や家族構成、希望エリアだけでなく、問い合わせ文面から読み取れる「温度感」や「検討段階」なども加味して分類できる体制が理想的だ。
たとえば、具体的な内見希望日を記載している顧客は既に高い意欲を持っていると判断できるし、逆に「まだ検討中」というニュアンスが強い場合は、情報提供に重きを置いた返信が適している。
返信のタイミングと中身が、ユーザーの状況にマッチしているかどうかが、その後のやり取りの成否を大きく左右する。
さらに言えばテンプレートが潤沢に用意できていると、担当が休みの場合でも代理で事務スタッフなどが返信することができる。
実際にかなり細かくテンプレートを作成することで、「業務の最適化」に上手く成功できた仲介会社も存在している。
さらに、店舗全体で返信対応のルールを明確に定め、それを徹底している点も見逃せない。
個人任せになっている店舗では、スタッフのスキルやモチベーションに応じて対応の質にムラが出る。
これに対し、反響対応のフローや返信時間の目安、使用するテンプレートの使い分けルールなどが明文化され、全スタッフに共有されている店舗では、常に一定以上の水準で顧客対応が実現できる。
組織として、反響返信に真剣に取り組んでいるかどうかは、こうした内部ルールの整備状況からも明らかになる。
上記のような代理対応も、こうした店舗全体のルールがあるが故にできる対応だ。
そして、最終的に反響返信率を大きく左右するのが、アポイント取得に向けた「内覧日の打診」である。
反響対応の初期段階で、具体的な内覧可能日を提示する店舗は、返信率が高くなる傾向がある。
なぜなら、顧客の多くは「いつ内覧できるか」に大きな関心を抱いており、それに対して先回りして提案することで、一歩リードした形になるからだ。
単に物件情報を送るだけではなく、「○月○日や○日で内覧のご希望はございますか?」という一文を添えることで、返信を引き出しやすくなる。
この一手間が、結果として大きな差を生む。
結局のところ、反響返信率が高い店舗とは、「スピード」「的確さ」「個別対応」「組織的な運用」「積極的な提案」のすべてを兼ね備えている店舗だということになる。
こうした店舗では、顧客との最初の接点を大切にし、問い合わせを「売上につながる第一歩」として真剣に捉えている。
その意識の高さが、細部の対応力に表れ、最終的には成果となって返ってくるのだ。