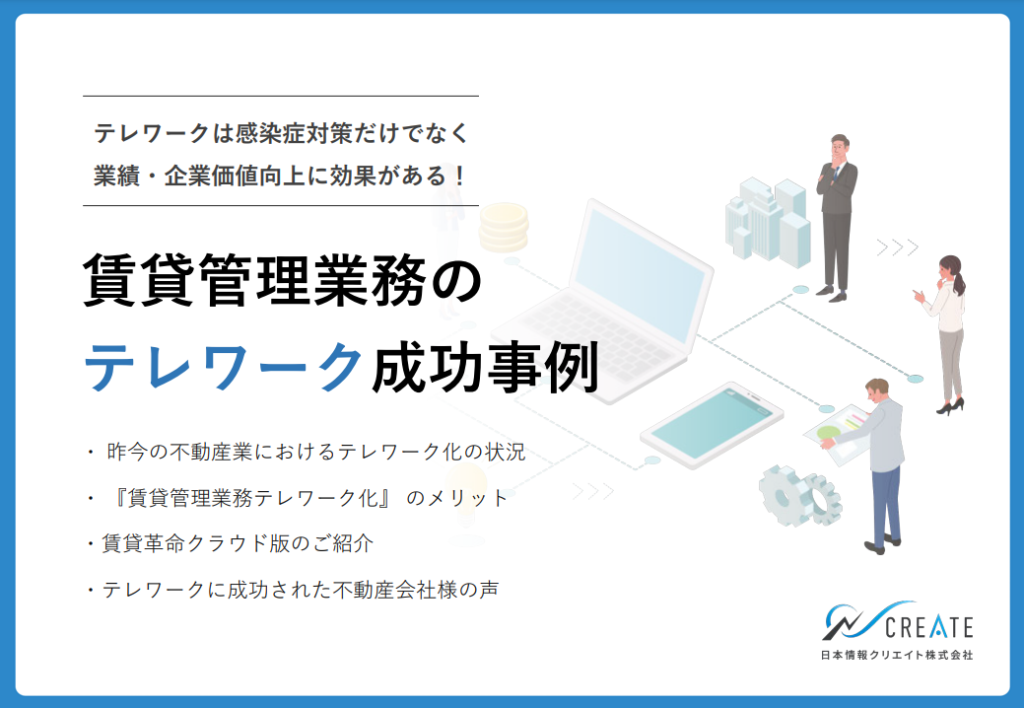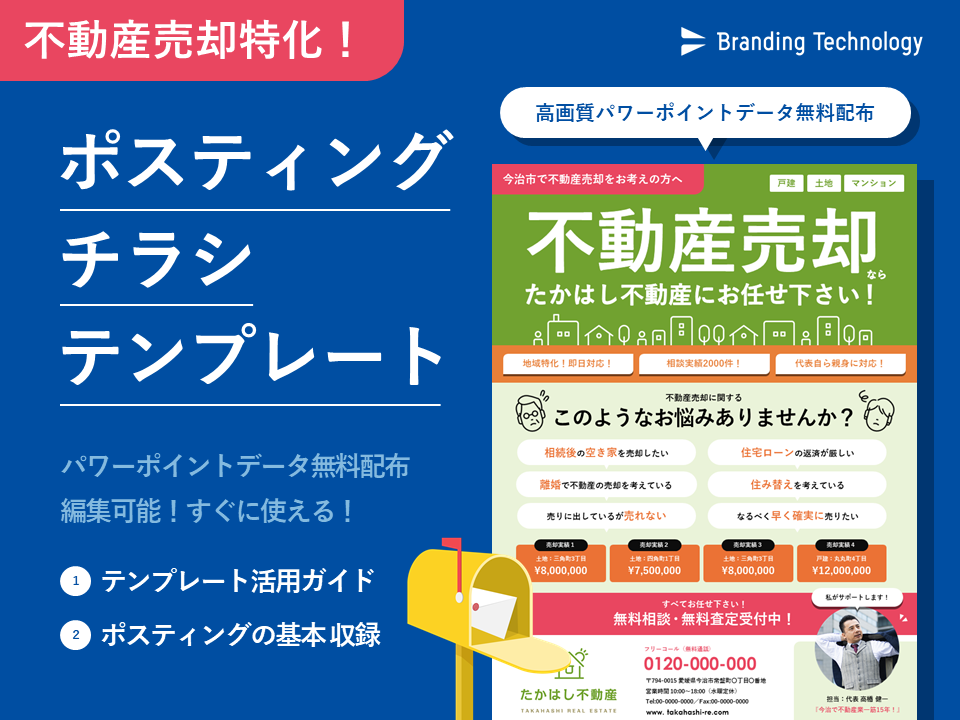年明けの繁忙期を迎える前に、不動産業界においては、賃貸仲介業でも賃貸管理業でも、必ず業務の見直しを行う必要がある。
年明けから春先にかけての繁忙期は、賃貸業界にとって年間で最も動きが激しい時期であり、この期間のパフォーマンスが年間の収益を左右すると言っても過言ではない。
しかし、その重要な時期を迎える直前のこの時期こそ、冷静に業務を整理し、無理や無駄をなくすための準備を整えるべきタイミングである。
繁忙期に入ってからでは改善の余地は限られ、現場は日々の対応に追われるばかりになる。
だからこそ、秋の今の時期に「業務の棚卸」と「最適化」を実行しておくことが重要なのだ。
まず、最初に着手すべきは「業務の棚卸」である。
これは自社のすべての業務を洗い出し、誰が、いつ、どのような目的で、どのくらいの時間をかけて行っているのかを明確にする作業だ。
仲介部門であれば、反響対応、物件紹介、内見、申込、契約、鍵渡し、アフターフォローといったプロセスを細分化し、各業務にどれだけの工数が割かれているのかを見える化する。
一方、管理部門では、退去受付、原状回復の手配、募集開始、契約更新、クレーム対応、定期点検など、日常業務が多岐にわたる。
どちらの業態であっても、実際に行われている業務を定量的に把握しなければ、どこに非効率が潜んでいるのかを見抜くことはできない。
棚卸の目的は「業務の可視化」であり、それがすべての改善の出発点になる。
業務の全体像が見えたら、次に行うべきは「繁忙期で想定される業務数の設定」である。
たとえば仲介業であれば、1月から3月にかけての問い合わせ件数、内見件数、申込件数、成約件数を前年データや市場動向から予測する。
管理業では、更新件数、退去件数、修繕依頼の発生件数などを見積もる。
この「業務量の予測」がなければ、必要な人員計画を立てることができない。
多すぎれば人件費が膨らみ、少なすぎれば顧客満足度が低下し、クレームや機会損失を招く。
繁忙期を乗り越えるためには、「最適な業務に最適な人数を配置する」ことが鍵となる。
ここで重要なのは、「最適化」とは単に人数を減らすことではなく、成果に直結しない業務を削り、本来注力すべき業務に人と時間を集中させることだ。
業務量の見通しが立った段階で、次に進めるべきは「自動化・効率化の検証」である。
近年はRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAIチャットボット、クラウド型の管理システムなど、業務の一部を自動化できるツールが急速に普及している。
例えば、仲介部門であれば物件ピックアップや追客のメール送信、内見スケジュール調整などはツールで自動化可能だ。
管理部門でも、更新案内や督促通知、定型修繕の発注管理などはシステムで処理できる。
こうした作業は人が行わなくてもよい「定型業務」であり、ここに多くのリソースを割いている会社は依然として多い。
繁忙期においては、こうした自動化の遅れが致命的な遅延やストレスを生む。
したがって、秋の今こそ自社がどこまで自動化できるのか、どのツールが実際に現場で効果を発揮するのかを検証する絶好の機会である。
自動化の検証を経て、次に明確にすべきは「人が注力すべき業務」と「注力しない業務」の仕分けだ。
これは単に自動化の可否ではなく、「人間が行う意味のある仕事は何か」という本質的な問いに向き合う作業である。
たとえば、顧客対応や提案業務、トラブル時の現場判断など、感情や状況に応じた判断力を求められる仕事は人にしかできない。
一方で、データ入力、確認作業、ルーティン的な資料作成などは、人が時間をかけるほどの価値はない。
限られた人的資源を最大化するためには、現場のスタッフが「どの仕事にエネルギーを注ぐべきか」を明確に理解しておく必要がある。
繁忙期において成果を上げる人とそうでない人の差は、この「注力の方向性」の明確さに大きく起因している。
次に、これらの業務整理の延長線上に位置づけられるのが「新しいKPI(重要業績評価指標)の設定」である。
従来、不動産会社では「反響数」「成約率」「稼働率」など、いわば“結果”を測るKPIが中心だった。
しかし、これからの時代は「どれだけ効率的に業務を処理できているか」「どの業務がボトルネックになっているか」といった“プロセス”に焦点を当てたKPIを設定することが求められる。
たとえば仲介なら「1件の契約までに要する平均対応時間」「追客から内見までの平均リードタイム」、管理なら「修繕依頼から完了までの平均日数」「クレーム対応の一次解決率」などが有効だ。
これらの指標を設定し、定期的にモニタリングすることで、現場の生産性が可視化され、改善の方向性が見えやすくなる。
さらに、こうしたKPIの再設計には、「データドリブン経営」の視点も欠かせない。
今や多くの不動産会社がExcelや紙ベースでの管理から脱却し、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)を導入し始めている。
データを基に意思決定を行うことで、感覚や経験に頼った属人的な判断を減らし、組織全体の再現性を高めることができる。
たとえば、追客に対する反応率を分析し、どの顧客層にどのアプローチが有効かを可視化できれば、営業効率は飛躍的に向上する。
また、繁忙期前に過去のトラブルや業務遅延の要因を分析し、改善策を講じることもできる。
これらはすべて「秋のうちにデータを整理しておく」ことが前提であり、繁忙期に入ってから取り組むべきではない。
最終的に、こうした業務棚卸・効率化・KPI再設計の一連のプロセスは、「組織の成長サイクル」を生み出すことに直結する。
毎年、反響数や成約率、稼働率といった表面的な数字だけを追っていては、本質的な成長は得られない。
むしろ、毎年秋に業務を棚卸し、ボトルネックを見つけ、改善策を講じる。
その積み重ねこそが、翌年の繁忙期の成果を大きく左右する。
業務改善は一度きりの取り組みではなく、継続的なループでなければ意味がない。
つまり、業務を見直すことは「繁忙期に備える準備」ではなく、「企業が成長を続けるための基礎体力づくり」そのものである。
繁忙期前の業務見直しは、単なる準備ではなく、自社の体質を強くするチャンスだ。
人員配置の最適化、業務の自動化、KPIの再設計を通じて、会社全体が「生産性の高い体制」に生まれ変わる。
繁忙期は待ち構えるものではなく、戦略的に迎えるものだ。
そのための第一歩が、まさに今この秋の時期に行う「業務の棚卸と最適化」なのである。