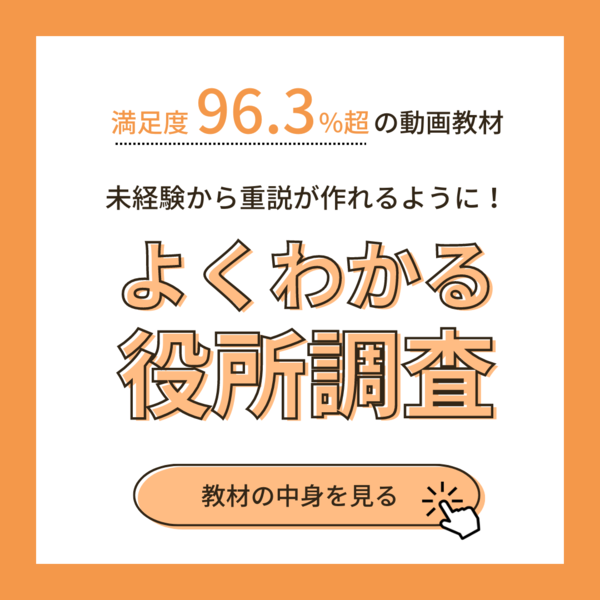2020年4月に、従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合」に変更になったことをご存じない不動産業者はいないでしょう。
では、家具付き住宅の場合に「家具」は契約不適合の対象になるかと質問されたらどうでしょうか?
「対象にはなりません」と答えますよね。
ですが、顧客から
といわれたらどうでしょうか?
上記のようなケースでは会社に迷惑をかけられないとばかりに「契約不適合にはあたらない、なぜなら……」と頑張るでしょうが、本当にその解釈は正しいのでしょうか?
インターネットの普及により「知識格差」は急速に解消されました。
従来でしたら、不動産など専門性の強い業務形態では、うろ覚えの法律知識を駆使して交渉を有利に進める状態が見受けられましたが、現在では買主の方が物を知っている場合があります。
うろ覚えの知識をひけらかせば簡単に足元を掬われます。
例えば住設機器の故障。
キッチンやトイレ・浴室などの住設機器は、中古住宅であれば状況報告書を添付して現状渡し、新築住宅の場合でも、設備機器メーカーの保証期間である24か月程度を目安としているのが一般的です。
ところが保証期間について予め説明しているにもかかわらず、期間経過後に発生した住設機器の不具合や保証期間について、「そんな話は聞いていなかった」と主張されるトラブルは非常に多く発生します。
根本的な原因として顧客の理解不足もありますが、私たちが正確に説明できていないこともまた原因の一つと言えるでしょう。
説明する側が正確に理解しないまま、約款を流し読みすれば、顧客もさして重要だと思わず、「そんな話は聞いていない」となるのでしょう。
私たち不動産業界の人間が、補償に関しての選別根拠となる「特定物」「不特定物」の違いを正確に理解して詳細に説明すれば、大きなトラブルに発展するケースは減少するでしょう。
今回は、そんな契約不適合の対象となる「特定物」「不特定物」について解説します。
「特定物」と「不特定物」って何?
まず不特定物の定義です。
と理解してください。
広義では一般的な消費財や日用品と解釈すればよく、商品に問題があった場合にはすぐに代替品を用意できるものです。
これらは1点ものではないですから、例えば通販で購入したパソコンモニターの動きが変な場合には交換してもらえば済みます。
交換したからといって商品価値が劣ることにはならないからです。
不動産の場合においては、一般的な住設機器などは全て「不特定物」に分類されます。
また、冒頭で例をあげた家具付き住宅の家具についても、普及品として市販され交換も容易な物は「不特定物」に分類されます。
それではウォールナット材などを使用したオーダー家具はどうでしょうか?
この場合には「特定物」となる可能性が高まります。
「高まる」と表現している理由なのですが、このあたりが線引きの微妙なところなのです。
そこで「特定物」の定義について解説します。
特定物とは「取引の目的物として当事者が“物”の個性に注目した物」です。
オーダー家具は室内の設置箇所を採寸し、木材の色合いを部屋の装飾によって変更するなど相応の労力をかけて発注した家具です。
この場合には1点ものと考えて差し支えがなく、「特定物」に分類できそうですが、「物の個性に注目」、つまりまったく同じ物を造ることが出来るかどうかにより判断が分かれます。
前記のウォールナットのオーダー家具にたいする「判断が微妙」であるとしたのはこのような理由からです。
これがアンティーク家具ですと、時代を経て風合いを出した木の色など再現をすることができませんので、「特定物」になります。
例えば建材メーカーなどで提供している造り付け家具などの場合、部屋の寸法に合わせた受注生産方式での制作になるのですが、このような商品の場合には、例え搬入商品に不具合があったとしても再度発注しなおすことにより交換がきく商品です。
壁への取り付けなどの手間もかかり、交換は比較的大掛かりになることもありますが、物の個性に注目した「一点物」とまでは言えないでしょう。
そもそも上記の例示したような受注生産方式は、セミオーダーです。
そこで多少あらっぽい分類になりますが、この記事の中では「特定物」「不特定物」を以下のように定義づけして話を進めていきます。
セミオーダーは「不特定物」
ただし、不動産の場合には「1点物」として分類されることから全て特定物になります。
買主の要望が一切反映されていない建売住宅で、全く同じような間取りと外観の家が並んでいても、不特定物とはなりません。
簡単に交換・返品が出来ないという原則によります。
「特定物」と「不特定物」賠償方法の違い
さて、なぜ分類の解釈にこだわるかというと、契約不適合時の賠償方法に違いが生じるからです。
この部分を正確に理解していないと、冒頭で上げた「私たちはアンティーク家具付き住宅というコンセプトに興味を持って~」につながるからです。
上記の場合には前項で説明した分類で分けると
アンティーク家具調の市販品であれば、交換が容易であることから「不特定物」
です。
不特定物の場合、保証期間内で不具合があれば補修、もしくは交換すれば簡単に決着がつきます(補修期間内に限ると言う点の説明は、契約時点までに正確に説明しましょう)
上記にたいして「特定物」の場合には、なんせ1点ものです。
そもそも簡単に代替品が準備できるのであれば特定物に分類されません。
さて、この特定物の不具合に関しての賠償責任として、皆様よくご存じの「瑕疵担保責任」や「契約不適合」が出てまいります。
この原則を理解して、2020年4月1日から施行された新民法から、売主の担保責任について考える必要があります。
改正ポイントを再確認する

ここで改正されたポイントをおさらいしてみましょう。
2. 担保責任の要件が、「隠れた瑕疵」から「契約不適合」へと整理された
3. 瑕疵担保責任効果は、債務不履行へ変更
4. 期間制限は1年以内に「通知」することで足りることになった。
これらの変更は全て「特定物」に対する法的責任についてですので、不動産はもちろんのこと、1点ものである美術品やアンティーク家具も含まれます。
通説ですが、売主の瑕疵担保責任は債務不履行ではなく「特別の法定責任」であると解釈されています。
特別の法的責任と表現するとつい構えてしまいますが、法律的な表現をするともっと分かりにくくなります。
瑕疵のある給付が、瑕疵の無い完全な履行?
矛盾していますよね。
法律家の間では、このように相反している表現を「特定物ドグマ」などと称しています。
ドグマとは宗教などにおける教義のことですが、そこから派生して「偏見的な説や意見」と解されています。
つまり法律的な独断的意見と揶揄している訳です。
この相反する文言を分かりやすく表現すると「1点ものなのだから、瑕疵が存在しても(例えばアンティーク家具の引き出しが経年劣化により開かないなど)それらを含んで引き渡しをすれば売主の責任は果たされる。なんせ、代替品がないのだから」となります。
この考え方からすると「瑕疵ある物」であっても、売主が引き渡しさえおこなえば債務不履行責任については認められないことになります。
ただこの原則論をそのままにすれば、「買主」が瑕疵の無い1点ものだと思い込んで購入した物に対して保証がされず一方的に不利益な状態におかれます。
そこで「法定責任説」という考え方が同時に存在します。
「対価の不均衡を正して、買主の信頼を保護する」という考え方です。
この解釈のうえに成り立つのが瑕疵担保責任です。
私たちの取り扱う不動産は、この「法的責任説」を土台として組み立てられています。
この法定責任説は「特定物売買」にのみ適用される考え方です。
ですからすぐに交換が可能な「不特定物」には、そもそも瑕疵担保責任が適用されないという考え方です。
ですが、勘違いしないでください。
不特定物にはそもそも「瑕疵の無い物を給付する義務」がありますので、不具合品をそのまま引き渡して良いと言うわけではありません。
上記の場合には、「瑕疵担保責任」ではなく「債務不履行」に該当します。
また法改正に伴い「特定物」にも「瑕疵の無い物を引き渡すこと」を債務内容として合意することが可能になった点には留意する必要があります。
合意することが可能になっただけですので、「瑕疵の存在しない物件」という表記を契約約款に盛り込むのはお勧めしません。
あらためて「隠れた瑕疵」から「契約不適合」への変更点を理解する
従来における不動産の「瑕疵」が、「隠れた瑕疵」であったことについては説明する必要もないでしょうが、「契約不適合」へと変更されたことにより解釈が変わりました。
「引き渡された目的物が、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき」に、売主が一定の担保責任を負うとの考え方です(562条1項)
では従来の「隠れた瑕疵」と、意味合いにおいてどれだけ変わったかというと実は変わっていません。
単に「隠れた瑕疵」という概念を、表現を変えることにより明確化することを目的としただけです。
この部分を正確に理解せずに、私たちは「法改正で大変だ」と騒いでいたのです。
それでは何が変わったのか?
法概念が明確になったことにより、明らかに変わったのが先に解説した「法定責任説」の明文化です。
従来の「隠れた瑕疵」と言う表現では、「法定責任説」と「特別の法定責任説」が混在することになり解釈があいまいでした。
当事者同士が独自に解釈をして、それが原因でトラブルになるケースが多かったのです。
法改正により「法定責任説」を「隠れた瑕疵の」の定義と定めたことにより、担保責任の効果が明確になりました。
つまり、不特定物に適用されていた修補請求・代替物引き渡し請求・不足分引き渡し請求(562条1項本文)を、「特定物」にまで範囲を広げたことです。
ただし「特定物」は1点ものであるとした場合に、代替物引き渡し請求は実現不可能です。
そこで実務的な解釈として「売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」としました。
簡単に表現すると「担保責任は認めるけど1点ものだから、代替品を用意することは出来ません。補修など他の方法で勘弁してね」ということです。
改正によるトラブル原因として、新たに発生すると考えられるのが「買主に不相当な負担」についての解釈です。
ですが、さいわいなことにこの条項については任意規定とされていますので、売主や、売主を代理する私たち不動産業者が異なる方法で履行の追完を特約することまでは妨げられていません。
契約解除についてはどうなった?
契約不適合による解除権の行使について、法律では特別の規定を定めていません。
売主担保権の法的な性質としては、「債務不履行責任」であるとされ、債務不履行による解除権(541条・542条)が適用されることになります。
従来の不動産売買契約書によく約款に記載されていた「契約をした目的に達することができない」という表現による制約は、法改正に伴い撤廃されています。
ただし何でもかんでも契約解除権が行使されればたまった物ではありません。
そこで、「債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽妙である時」は、契約解除権の行使をおこなうことが出来ないとされました(541条但書)
問題となるのが「社会通念上軽妙」の判断についてですが、法律で明確に定められてはいません。
つまり、この部分についての記載内容によって引き渡し後のトラブルが予見されることから、曖昧にせず精査して定めておくことが大切です。
損害賠償についての考え方。どこまでが適正範囲

旧法である「隠れた瑕疵」でも新しい「契約不適合」でも、損害賠償に関する特別の規定は存在していません。
その適用は損害賠償の一般規定である415条が適用されるのですが、この債務不履行責任による賠償請求権が拡大解釈されることにより、問題が発生することになります。
例えば、新築住宅であれば「こんな不完全な状態であれば、そもそも購入していなかった」という損害賠償請求権をたてにとった買戻し請求です。
不動産の場合に買戻し請求をすんなりと飲むことは出来ませんから、契約不適合が認められた場合には何等かの金銭的な和解、つまり代金減額請求などにより対応することになります。
563条においては代金と目的物の対価的均衡を維持するという観点から代金減額請求を認めるという傾向が高まりました。
代金減額請求権」は「損害賠償責任」と異なる、売主の無過失責任とされています。
この代金減額請求権は「買主が事実を知った時から1年以内に行わなければならない」とされています。
また減額請求権・損害賠償請求権は、従来は瑕疵の内容を具体的に特定することが求められていましたが、契約不適合では「通知する(566条)」だけで足りるとされていることに注意しなければなりません。
例えば「ドアの開きが急に悪くなった。家が傾いているのではないか」などの根拠なき申し立てが有効とされるからです。
根拠なき申し立ての場合においても、私たち不動産業者は対応をしなければならなくなったことから、理論武装の必要性があるのです。
そのためにも契約不適合の「消滅時効」について正しく理解しておく必要があります。
平成13年11月27日民集55巻6号1311項の判例により、契約不適合の消滅時効が明確になりました。
行使できる客観的起算点は物件引き渡し日、そこから10年を経過した時点において契約不適合にかんする消滅時効が成立します。
また、その間において契約不適合に関する箇所の指摘は「発見から1年以内の行使」とされていますが、その部分にも5年間という消滅時効が適用されます。
主観的起算点から5年(契約不適合箇所を指摘しないまま、5年間の経過で消滅する)
まとめ
「瑕疵」から「契約不適合」へと変更され1年が経過しました。
従来の瑕疵担保責任と比較して売主責任が明確に定義されたことにより、私たち不動産業者は契約関連書類の容認事項欄などの記載については、詳細でかつ具体的な記載を行うように注意しなければなりません。
特に気を付けたいのが、「近隣関係の騒音」などです。
「私たちは、この住宅を購入して生活することにより静かな環境で生活できると思っていた。ところが、夜間に近隣から大音量の音楽が毎日のように聞こえてくる。これは契約不適合に該当する」と言った主張もあり得ることになります。
中古住宅の場合には、売主からのヒアリングを詳細に行い、聞き取り結果を正確に記載し説明するなどよりいっそうの配慮が必要とされます。
契約不適合で具体的な指摘要件が排除されたということは、そういうことです。
将来的なトラブルが予見される内容については、詳細に漏れなく買主に伝えておくことが大切です。
またそのようなクレーム発生時に迅速に対応出来るよう、私たち不動産業界に従事する者は、「特定物」と「不特定物」の定義と「契約不適合」の消滅時効などについて正しく理解し、問題解決にあたる必要があるでしょう。