
皆さんご存じのように地積測量図は必ず存在しているものではありません。
存在していても、作成年度が古い物は信憑性に欠けます。
地積測量図が存在しないもしくは信憑性に疑義が生じる図面しか存在しない状態の物件を扱う場合、境界確定測量と地積更正登記を実施して間違いのない面積で売買契約を締結するのが最も安全です。
この考えに異論のある方は少ないでしょう。
ですが問題は費用です。
境界確定測量や地積更正登記は物件面積や境界鋲等の有無、隣地所有者の居住地やそれらを調査するために必要とされる労力などにより費用が変わります。
問題がなく、スンナリといく場合でも30万円以上が目安です。
この費用は通常、土地所有者の負担となりますから、所有者としては可能であれば費用負担せず売却したいのが本音です。
そのような要望があれば公簿取引により売買契約を締結することになるのですが、決済後、実測した場合において発生する公簿との差異についての精算方法を明確にしておかなければ大きなトラブルに発展します。
今回はそのような観点から、実測の差異によるトラブル事例も交え公簿取引に潜む危険性について解説します。
契約書の記載事項に注意
平成11年12月15日に名古屋高等裁判所で判決(平成11・ネ・434)された内容を不服として、上告しましたが最高裁において棄却(平成12・受・372)された判例です。
地積測量図が存在しない住宅地を、公簿面積が実測と等しいと信じ、坪単価で金額を定め契約を行い決済まで終えました。
その後、実測をしたところ登記簿上177㎡であった土地は実際には167.79㎡(不足9.21㎡)しかなく、減少した分の金額について減額請求(返還)を求めた事件です。
判決では差異による減額請求を求めた原告の主張が認められ、それを不服として上告した被告(上告人)の請求は棄却されましたので、減額精算をしなければならないと確定した訳です。
裁判における原告と被告の主張、及び判決に至る論旨は事項で詳しく解説しますが、ここでは対象面積に増減が生じる可能がある場合の契約約款について解説します。
冒頭で解説したとおり信頼の置ける精度の地積測量図が存在しない場合、境界確定測量と地積更正登記を行うのが最も安全ですが、費用を負担したくないとの売主要望を汲み取れば公簿取引しかありません。
公簿面積は、地積測量図が存在しないもしくはその精度が低い場合、実測と差異が生じる可能性は容易に予測されますから、実測した場合における差異について精算をおこなうかどうかについては契約前に予め契約当時者と相談し、その内容を契約書における約款等で定めておく必要があります。
(財)不動産取引推進機構が作成した契約書を参考に、国土交通省庁が標準契約書の例として公開している売買契約書においても公簿と実測の差異は精算しないとされており、この標準契約書を参考として作成された(公社)全日本不動産協会の契約書においても下記のように売買対象面積に差異が生じても異議申し立てせず、何らの請求もしないとされています。
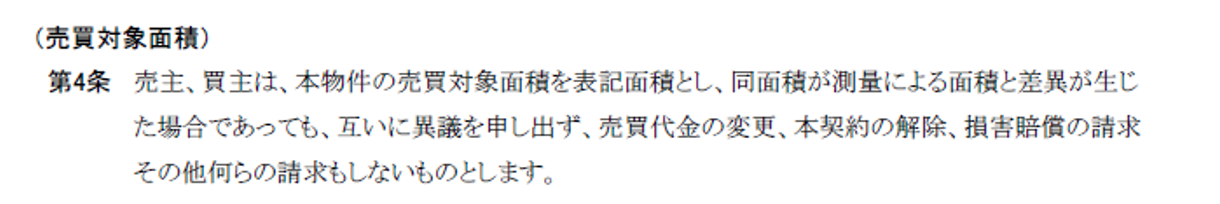
事項で解説する判例において使用された契約書の約款に、売買対象面積についてどのように記載されていたかは示されていませんが、おそらくは標準契約書を使用していたのではないかと推察されます。
それではなぜ、実測による差異の精算について争われ、減額請求権が認められたのでしょうか?
ポイントは数量指示にあたるかどうか

裁判要旨について説明します。
物件は市街化区域内にある約50坪の更地です。
売買契約書には目的物件の表示として公簿面積のみが記載されていました。つまり典型的な公簿取引です。
この土地は住宅建築を目的として売買され、売買代金については公簿による㎡数が、実測と同等であるとの根拠のもとに単価を定め、それに面積を乗じることにより算出されました。
お互いの主張を見ても契約の当事者双方は実測面積が公簿と等しいとの認識しており、その後、実測を行っても差異は生じないとの認識により締結されています。
残代金を支払い所有権移転も終え、買主が建築に先立ち実測をおこなったところ、等しいと思っていた公簿面積177㎡は実測で167.79㎡(不足9.21㎡)しかなく、支払い済み金額が過大であることからその一部返還を求めるとして減額請求の合否について争われました。
前項で解説したように、契約当事者が合意して標準契約書における約款を採用すればこの場合でも減額請求はできないはずです。
公簿と実測には差異が生じる可能性は容易に予測できることがからです。
ですが、価格交渉や契約までの経緯などにおいて本件契約は「数量指示売買」にあたると原告が主張し、一連の主張と証拠からそれが認められました。
つまり差異の精算が原審である名古屋高裁で認められ、それを不服として被告(上告人)が上告した最高裁小法廷で棄却されたことにより名古屋高裁の判決が確定しました。
筆者の知る限りでは民法で定める数量指示売買であっても、契約当事者間で数量増減による代金精算が合意されていなければ代金の増額請求はできないはずです。
ですからこの裁判は、一連のやり取りにおいて数量指示売買であると当事者双方が認識する内容であったのか否かを争った事件と言い換えることができます。
契約不適合責任は民法第565条で定められた「移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任」として、さらに民法562条_追完請求権・563条_代金減額請求権・民法415条_損害賠償請求権などで構成されます。
原告が主張した数量指示売買であるとの根拠は以下のようなものです。
1. 広告に公簿177㎡(53.45坪)、価格3640万円、坪単価68万円との記載があった。
2. 上記坪単価に対し、建築依頼会社であるD住宅を通じ価格交渉を行ない、坪単価65万円の値下げ回答が得られた。
3. 住宅は一旦自社で物件を購入し、その後、購入価格と同等で原告に売却する予定であることから原告とD住宅との間で専属専任媒介契約を締結した。媒介契約書の目的物件の表示欄には実測面積177㎡・公簿面積も同様と記載されていた。
4. 被告とD住宅との間においても専属専任媒介契約が締結されているが、目的物件の表示欄には公簿面積177㎡としか記載されず、実測については空白であった。
5. 原告がD住宅に実測図を要求したところ、実測が177㎡である旨が手書きで記載された公図を交付され、この図面により本件土地が177㎡で間違いないと思い、実測図の要求はしなかった。
6. 契約締結前に重要事項説明書による説明が行われたが、重要事項説明書面には登記簿177㎡(53.45坪)の記載はあったが、実測は空欄のままだった。
7. 重要事項説明書における建築面積の限度には建ぺい率として「敷地面積177㎡×60%=106.2㎡」容積率として「敷地面積177㎡×200%=354㎡」と具体的に記載されていた。
8. 売買契約書の目的物件の表示には「すべての面積は公簿による」との記載がされていたが、D住宅による説明はなく、契約当事者双方においてもその意味が確認されることはなかった。
さてその後、原告(買主)により実測が行われ、公簿面積よりも実測面積が少ないことが発覚し、不足分の減額請求を求め提訴されたわけです。
合議制において判断が分かれる内容である
原審である名古屋高等裁判所は前項の原告の主張と被告の反論を踏まえ「本件売買契約書における土地公簿面積の記載は、実測面積が少なくとも公簿面積と同じだけあるという趣旨でされたものであり、売買代金の額は本件土地の実測面積が公簿面積どおりにあるとして決定されたものであると解釈し、本件売買契約はいわゆる数量指示売買にあたる」と判断しました。
前項でも触れたように被告側(上告人)は、原審による契約解釈及び判断は経験則に違反しており、民法565条(数量指示売買)の解釈を誤っていると最高裁に上告しましたが棄却されました。
前項における原告の主張によれば、たしかに媒介に入ったD住宅において媒介契約書の記載事項や、売買契約書の記載方法とその説明等において漏れ落ちがあることは否めませんが「公簿と実測の差異は精算しない」と記載された標準契約書を使用していたと過程すれば、何ともやりきれない判断です。
裁判所の判例情報において売買契約書に差異が生じた場合の精算について記載があったのかについては記録されておらず、判断ができません。
もつとも原審を不服として上告し結果として棄却されてはいますが、最高裁小法廷は定数3の合議制ですが、裁判官の1名は数量指示売買にあたらないと反対意見を投じています。
「当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、一定の面積・容量・員数または尺度があることを売主が契約において表示し、かつこの数量を基礎として代金額が定められていることが必要とされるが、本件売買契約において売主は一定面積があることを契約において表示したものと解すことはできない」というのが反対理由です。
精算トラブルを防止するには

判例におけるケースでも、公簿と実測の差異が生じた場合における精算について記載された標準契約書を使用する場合には、契約当事者当方に下記のような内容を念押しすることで同様のトラブルを未然に防止することができるでしょう。
1. 公簿と実測それぞれの意味合いの違いを契約当事者双方に正確に説明すること。
2. 売主に対しては後日紛争の防止のため、境界確定測量や地積更正登記を推奨すること。
3. 契約締結前であっても、契約書記載の約款を利用して「公簿取引の場合、引き渡し後、実測による差異が生じても精算はされない」旨を説明し、その理解の程度を確認すること。
4. 引き渡し後の実測による精算を契約当事者双方が合意した場合においては、引き渡し後実測までの期日、差異が生じた場合の㎡金額、精算方法等についての取り決め予め行い契約書もしくは別紙覚書等に記載し、双方所持すること。
5. 契約書や添付する公図等についても、公簿取引であることが一目で分かるよう配慮し、後日、誤解まねく不要な記載等をおこなわないこと。
まとめ
筆者は32年間、不動産業に準じこれまでに何度も公簿と実測による差異が生じた場合における精算について業務を行ってきましたが、それにより大きなトラブルが生じたことは一度もありません。
それは精算トラブル防止のための措置を必ず実施して、信頼のおける精度の境界確定測量や地積更正登記が実施されていない限り、差異が生じるのは必然だと考えているからです。
ですから公図ではなく国土調査法に基づき作成された法14条地図が存在し、現地復元性(地図を利用して境界を復元できること)があったとしても、境界確定測量等を実施しなければ公簿との差異は当然に生じることも説明しています。
裁判においても意見の分かれる数量指示売買の構成要件ですが、私達、不動産業者としては紛争を未然に防ぐ配慮をする必要があると言えるでしょう。


































