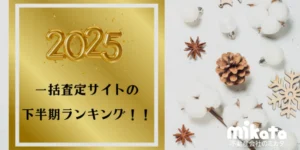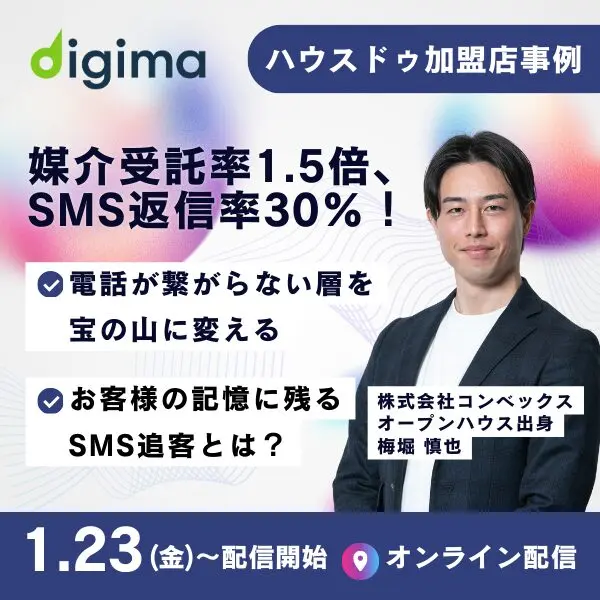私たち不動産実務家の元には、相続財産に不動産が含まれるがゆえに、解決の糸口を見失った相談が絶えません。
相続案件は、単なる登記名義の移転手続きではありません。
故人の想い、家族間の感情、経済的な利害、さらには複雑な法律や税制の壁が絡みあい、極めて属人的な課題を内包しています。
相続人が少数で、かつ遺産分割の対立が生じていない事案は円滑に進行するでしょう。
しかし、代襲相続が発生し相続人が多数となり、さらには連絡不通や居所不明の相続人が存在するなど、権利関係が複雑に錯綜する場合は遺産分割協議の組成と利害調整に、極めて多大な労力と時間を要します。
その結果、必要とされる高度な知見と膨大な調整労力は、しばしば事業としての費用対効果に見合いにくい、いわゆる「割に合わない」案件として敬遠されがちです。
さらに深刻な問題は、コンプライアンスです。
不動産実務家として遺産分割協議に深く介入し、分割の主導、相続人間の仲裁や和解といった法律事務を行った場合、非弁行為(弁護士法第72条)に抵触するリスクを伴います。
調整行為そのもので報酬を得なければ違法とされる可能性が低いとはいえ、この領域が極めて危険な一線であることは認識すべきです。
しかし、コンプライアンスを遵守しつつこの難局を解決に導けるか否かが、不動産プロフェッショナルとしての真価を問われる局面です。
可視・不可視の困難を予見し、それを乗り越える対処能力を発揮することこそが、皆様の専門性とコンサルティング能力の真価を世に問い、案件の成否を分けるのです。
本稿では、筆者がこれまで取り扱った複雑な事例を踏まえ、相続問題を円滑な解決へと導くために不可欠な高度な知見と実務上の注意点について詳述します。
相続案件特有の「三つの困難」
相続案件が他の不動産取引と一線を画すのは、主に以下三つの構造的な困難が存在するからです。
1. 感情的な困難(エモーショナル・ハザード)
相続は被相続人の死が契機となるため、遺族の心には悲しみ、後悔、時に軋轢が生じます。
特に、「長男だから」といった時代に即さない家督相続制度の意識や、被相続人への貢献度に基づく主観的な主張が、法定相続という客観的なルールと衝突します。
●遺産分割協議の長期化と膠着:
筆者の経験上、相続財産が現金や預貯金が主体の場合、取り分で多少の悶着はあっても、問題はさほど大きくなりません。
一方で、不動産が主体の場合、単独名義での利用・処分という理想論が、感情的・経済的要因で頓挫します。
●共有名義のリスク:不動産を共有名義にしてしまうと、「売却したい者」と「残したい者」の意見対立や、共有者全員の合意を要する有効活用が困難となり、結果的に塩漬けリスクを生み出します。
卓越した不動産業者としては、相続人全員の真意を深く探ると同時に、感情的なバイアスを取り除き、経済的合理性に基づいた着地点へと誘導するファシリテーション能力が求められます。
2. 法的・権利関係の困難(リーガル・コンフリクト)
相続不動産には、多くのケースで通常の売買物件にはない特有の法的リスクが内在しています。
●登記の困難性:
移転登記がなされず長期間放置された場合、現行住所と登記情報記載の住所が不一致であるケースや、数次相続により権利関係が複雑化しているケースが散見されます。
また、未登記建物の存在や違法建築の有無も、所有権確定の大きな障害となります。
●権利関係の複雑化:
遺言書の法的有効性、特別受益(生前贈与など)、寄与分(貢献度)といった要素が加わると、単なる法定相続分計算では解決できません。
特別受益はその内容を精査する必要があり、貢献度を金額で換算するのは極めて困難だからです。
●相続人調査の限界:海外在住、音信不通、あるいは居所不明の相続人が存在する場合、戸籍調査と連絡調整に多大な時間と費用を要し、案件全体のリードタイムを大幅に延伸させます。
3. 税務・評価上の困難(ファイナンシャル・チャレンジ)
相続税の申告期限(原則10ヶ月)は、上記1・2の問題が生じていても、否応なしに迫るタイムリミットです。
●「小規模宅地等の特例」適用判定:
居住用・事業用地の評価減特例は、適用要件が細かく、遺産分割協議の結果によって適用可否が左右されます。
節税効果が大きいため、この特例の適用を巡って協議がさらに難航する場合があります。
●不動産の評価:
相続税申告に用いる評価額(路線価・固定資産評価額)と、市場における実勢価格には、往々にして大きな乖離が存在します。
この評価差が、売却時の譲渡所得税や、分割協議における公平性の認識に影響を及ぼします。
過去に、相続人各位が異なる不動産会社に査定を依頼し、その査定額に大きな差があったことで協議が難航したケースもありました。
このように、私利私欲が絡み合う問題をどのように解決するかが、不動産プロフェッショナルの手腕が問われる局件です。
卓越した不動産業者には、これら感情・法律・税務のトライアングルを同時に、かつ迅速な解決へと導く総合的な知識とネットワークが求められるのです。
実例:未登記不動産の解体リスクと手続き倦怠
相続不動産に老朽化した建物が含まれ、相続人による管理が困難な場合は売却が合理的です。
その場合、古家付き宅地としての売却か、更地渡しを条件とするのがセオリーですが、建物が未登記の場合は極めて慎重な対応が必要です。
ここでは、適切な手順を経ていれば回避できたはずの事例を紹介します。
【事案の概要】
相談者A様の父親(故人)が所有していた財産は、木造一戸建て(登記情報上の所有者は父)とその敷地のみ。相続人はA様と弟B様の二人。
特筆すべき事実
1. 父親は数年前から介護施設に入所していました。その間、建物は誰にも管理されず老朽化が進行したため、市から修繕に関する指導がなされており、放置すれば特定空き家に指定される可能性がありました。
2. 父親が数十年前に増築した部分が未登記のままでした。
3. A様とB様は、「建物を解体し、更地にして売却する」点については口頭で合意していました。
4. 遺産分割協議及び相続登記は未了。
案件の進行と直面したリスク
A様は、特定空き家の指定を回避するため、遺産分割協議や相続登記を待たずに、B様の承諾を得ないまま、ご自身の費用で建物の解体工事を先行しました。
リスク① 共有物の変更行為に関する金銭請求
民法上、共有物(この事案では、未登記ながら外形的要件から共有財産)の「変更行為」を行うには、原則として共有者全員の同意が必要です。
2023年4月1日施行の改正民法で軽微な変更については要件も緩和されましたが、解体はこれに該当しません。

B様は、口頭での合意は認めたものの、「解体費用が高すぎる」と主張し、A様に対し、持分権侵害に基づく金銭請求を提起しました。
【教訓】 共有状態にある不動産(登記の有無にかかわらず)に物理的な変更行為を行う場合、具体的な費用や依頼先、変更内容などを書面に記載し、共有者全員の同意を得る必要があります。
口頭合意は後から容易に覆されることを肝に銘じるべきです。
リスク② 未登記物件の解体による登記懈怠
建物を解体した場合、解体から1ヶ月以内に滅失登記を申請する義務(不動産登記法第57条)があり、義務を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
本件建物は増築未登記部分が存在し、かつ相続登記が行われていませんでした。
注意点① 登記されている部分の滅失登記:相続登記が未了の状態で滅失登記を行うには、相続人全員からの委任状および相続を証明する書面(遺産分割協議書または法定相続情報一覧図)が必要となります。A様は、これらを準備しなかったため、申請が受理されませんでした。
注意点② 未登記部分の扱い:未登記部分を含む建物を解体する場合、滅失登記の前提として、未登記部分の「表題登記」を相続人名義で先行して行う必要があります。法務局からこの指導を受けた結果、滅失登記の義務違反に加え、表題登記の懈怠という二重の問題が顕在化しました。
【教訓】 分割協議が整わない状態で未登記建物の解体を先行する場合、土地家屋調査士に依頼して被相続人名義の表題登記を行い、所有権を確定してから解体するのが安全です。
これにより、第三者の建物である可能性や、手続き遅延による過料リスク、管理不全空き家の指定などを回避できます。
実務家の対応戦略
前項の事例では、適切な手順に基づかず独断で解体を行ったことにより事態を深刻化させました。
多くの場合、問題が拗れてから相談が持ち込まれる現実を踏まえ、卓越した不動産業者であるためには、以下三つの戦略を講じ備える必要があります。
1. 「フルコンサルティング」体制の構築
不動産業者単独で問題を解決するのは困難です。
私たちは、以下の専門家を束ねるオーケストラの指揮者となるべきです。
税務・評価:税理士
紛争・調停:弁護士
測量・登記;土地家屋調査士
例えば、未登記が判明した際には、顧客にリスクを説明し了解を得たうえで、速やかに土地家屋調査士を関与させ表題登記の準備をすると同時に、司法書士に相続登記と滅失登記の準備に着手してもらいます。
このように、ワンパッケージで事案に当たるチーム体制を構築することで、早期かつ安全な解決に寄与できます。
2. 「合意書面」の重視
遺産分割協議がまとまらない限り、物件の売却は不可能です。
民法206条では、不動産が共有状態である場合では、各共有者は自己の持分について処分(売却・贈与など)できると定めています。
しかし、所有権の割合が確定しない段階では、この権利を行使できません。
そのため、不動産業者は弁護士の指導・助言を得ながら、以下の点を相続人に提案し、合意した内容は即時、書面に残す必要があります。
これは、遺産分割協議書とは別の合意内容を記す書面です。
表題は合意書、覚書、確認書、約定書などいずれを用いても構いませんが、日付の記載と、第三者が見ても内容が理解できる表現とすることに留意し、相続人の署名(捺印は絶対条件ではありませんが、あった方が確実です)を得る必要があります。
●分割方法の多様性:換価分割(売却)だけでなく、代償分割(特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に対し現金で補填する)や共有(最終手段)のメリット・デメリットを丁寧に説明し、経済的合理性と公平性に基づいた選択肢を提示します。
●費用負担の明記:解体や賃貸転用するための手直しなど、費用負担が生じる行為を先行する場合、誰が、どの割合で負担し、売却代金からどのように精算するのかを、遺産分割協議書とは別に「費用負担および精算に関する合意書」として明確に書面に残すことが肝要です。
3. 「時間軸」のコントロール
相続案件は時間との闘いです。
長期化するほど新たな問題が発生しやすく解決が困難となり、結果的に「塩漬け」となるリスクが高まります。
●初期調査の徹底:案件受託の初期段階で、法務局での登記関連調査はもちろん、固定資産税の課税台帳や市区町村での建築確認台帳の確認を行い、登記内容の齟齬や適正性・再建築の可否などについて徹底的に調べ上げます。
●申告期限の留意:
相続税の申告期限(10ヶ月)から逆算し、相続人調査、遺産分割協議、売却活動の各工程に厳格なデッドラインを設定します。
それにより、相続人に対する強いリーダーシップを発揮してタイムマネジメントを行うことで、問題の長期化と複雑化を防止します。
まとめ
相続案件は手間がかかり、非弁リスクも内在するため、敬遠されがちな領域であるのは事実です。
相続人の意見が整わず長期化した場合、「労多くして功少なし」の成句どおりの結果に終わるリスクが高まります。
しかし、だからこそこの領域は、私たちが高度な専門性とコンサルティング能力を発揮できる最大の機会となります。
案件を単なる取引で終わらせるのではなく、相続人家族の未来をも見据えた総合的な解決へ導くこと、その実現を阻む「困難」を乗り越えることこそが、皆様が地域社会から信頼され、他社と明確な差別化を図る確固たる礎となるのです。