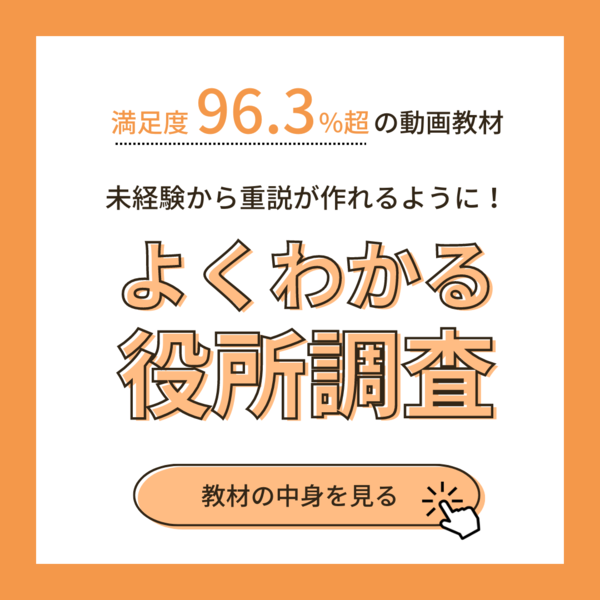私達不動産業者は再販の目処が立ちそこに利益が生まれるのなら、資金に余裕がある限り積極的に買い取りを検討するでしょう。
その際の購入価格は相場よりも安い方が良いのは当然で、安く買取ができるほど再販時の利益が期待できます。
ですが、せっかく安く買取ができたのに、その後、買取金額が不服であるとして裁判に提訴されると「著しく廉価であり不当」とされ、売買契約自体が無効にされた判例が存在するのはご存じでしょうか?
売却を希望していない顧客の自宅に、長時間居座り脅迫に近い形で契約締結した場合や、詐欺による契約が無効とされるのは理解できますが、金額も含め双方が合意すれば何も問題はないはずです。
そもそも公序良俗に反しない限り、当事者の意思表示が合致する限り「契約自由の原則」が民法の基本だからです。
買取額が一般的な流通価格より安くても、何も問題はないはずです。
ところが市場価格6割程度で行った買取契約が「暴利行為」として無効とされた判例(大阪高判21.8.25)が存在するなど、安く買取できたと喜んでいたら、その後の裁判で無効とされる可能性があるのです。
そこで今回は具体的な判例を参考に、一体、何が問題であったのかについて考えて見たいと思います。
善意無過失の主張が認められず
分かりやすく解説するため、多少、詳細を省略しますが平成30年3月の東京高裁による判例(判例時報2398-46)です。
事件のあらましは以下のようものです。
被告であるAは賃貸アパートを建築する資金を金融機関Bから借入していました。
その不動産を担保として3,600万円借入の借入をしていましたが延滞し、金融機関Bから「期限の利益の喪失」が宣言され、競売申し立てを行う方針であるとの通知を受け取ります。
気持ちも焦っていたのでしょう、知人から紹介を受けた法人C社(不動産業者ではありません)との間で6,000万円の売買契約を締結し、所有権移転を行いました(この時点では金融機関Bの根抵当権は抹消されていません)
また所有権移転は行われたのですが、金融機関Bへの残債は完済されていません(というよりも、残代金が支払われていないのです。その状態でなぜ所有権移転に応じたのかまでは資料から確認できません)
その後、法人C社は不動産業者であるD社との間で、本件物件について1億5,000万円の売買契約を締結します(C社の買取金額は6,000万円ですから、確かに不当に安い金額であることが分かります)
不動産業者D社は契約締結の翌月にC社にたいし全額の支払いを行い、C社はその決済金により金融機関Bに返済、根抵当権は抹消され所有権もD不動産業者に移転されました。
所有権移転後も前所有者Aが建物を占有していたことから、不動産業者Dは原告として被告をAとして建物の明け渡しと損害賠償の支払いを求め提訴しました。
東京高裁はこの訴えにたいし「個人所有者であるAと、法人である Cとの売買契約はその金額が著しく廉価であることから公序良俗に反し無効。また不動産業者Dについても善意無過失の第三者とは認め難いものであるとして請求を棄却する」といったものでした。
一体、事件にはどのような背景があったのでしょうか。
指摘された問題点

法人C社は買取金額が不当に廉価であり、またD不動産業者との決済を終えるまでの間、Aにたいして内入れ充当金以外、現金を渡していないとの指摘にたいし「売買金額以外にAに対する貸付債権を有しており、売買残代金についてはそれと相殺した」と反論しましたが、貸付債務と相殺したことを示す書類等は確認できず、またそのような支払いを約した証拠も存在しないとして退けられました。
さらに裁判所は「法人C社が不動産業者Dと契約した金額である1億5,000万円は、契約において作成された複数の不動産鑑定書により妥当な金額であるといえるが、それと比較した6,000万円というAとの売買価格は、これと比較しても著しく廉価であり、またそれさえも実際に支払われていない」と指摘しました。
被告Aがそのような著しい廉価で法人C社と契約を締結したのは、金融機関Bから「期限の利益の喪失」が宣言され、かつ競売申し立てを示唆されるなど、論理的思考能力や判断能力が相当程度低下していたことによると強く想定されるとしました。
さらに法人C社にたいしては、不動産業者Dと売買契約を締結したことにより6,000万円以上の莫大な利益を得ており、被告Aの切迫した窮状に乗じた公序良俗に反した暴利行為であるとしました。
確かに一連の流れから、このような裁判所の判断は理解出来るのですが、相応の金額で購入した不動産業者Dによる「善意の第三者」であるとの主張が、なぜ認められなかったのでしょうか?
善意の第三者であれば、権利外観法理(民法第94条2項_虚偽表示からの類推)が適用されるはずです。
民法第94条2項で「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定められていることから、不動産業者Dが主張する所有権はしごく真っ当であると思われます。
ところが、不動産業者Dは被告Aと法人C社との間で締結された契約内容を認識し、また契約に先立って直接被告Aと面談していたことがあっとして善意無過失にはあたらないとされました。
このあたりの詳細な内容まで確認することはできないのですが、不動産業者であれば購入前の現地踏査は基本ですし、その際に占有者が存在して偶然、顔を合わせれば「その後の立ち退き交渉」をスムーズに行うため挨拶の一つもするでしょう。
また占有者が存在しているのですから、売主である法人C社にたいし所有に至った経緯を確認するのも普通です。
筆者が不動産業者であるからかもしれませんが、不動産業者Dに同情します。
決済金の1億5,000万円を支払い、さらに裁判に要する費用や手間をかけ結果としては徒労に終わった訳ですから(当然に法人C社に対しては決済金の返還と損害賠償について責任追及していることと思いますが)
まとめ
過去判例を調べれば購入金額が著しく廉価である場合において、公序良俗に反して無効とされたものが幾つか確認することができますが、どの程度の金額が暴利行為として無効とされるかについては、具体的な目安となる基準はありません。
売却時に「売り急ぐ理由」が存在しているなど様々な理由も斟酌されているようですが、リースバックの買取金額が著しく廉価で不当だとの相談が国民生活センターに数多く寄せられていることや、認知能力が低下した高齢者のマンションを市場相場の35%程度で買取ったことが不当であるとして、市場価格との差額について損害賠償が認められた判例(東京高判平27.4.28)も存在していることから、ただ安く購入できたと手放しで喜ぶことはできません。
買取をする場合にできる限り安く購入したいと考えるのは当然ですが、買取金額を提示する場合に一般的な流通価格も併せて説明し、そのうえで急いで現金が必要な理由も勘案し双方が納得できる金額で折り合いをつけることが大切なのでしょう。
くれぐれも市場価格等の根拠を著しく低く見積もるなど、作為があったと指摘されるような行動は避けるのが無難だと言えるでしょう。