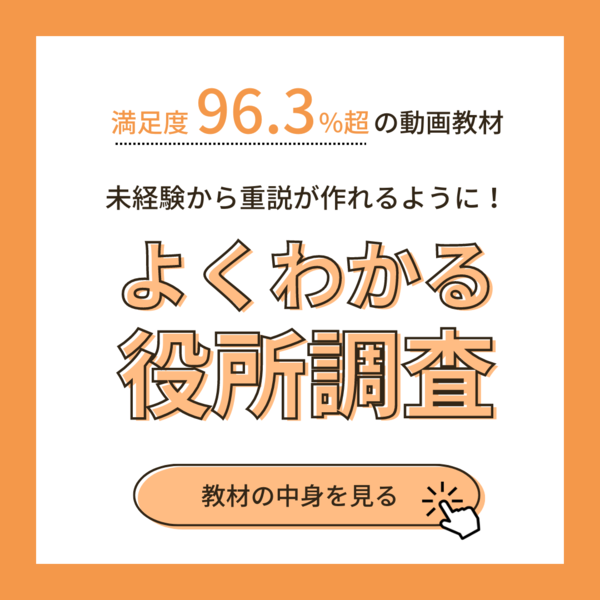契約は、必ずしも書面による必要はありません。口頭(諾声契約)や、明確な返事がない場合でも成立することがあります。
民法第522条では、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾したときに成立する」とし、さらに、第二項で「契約の成立は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定しています。
この条文から分かるように、意思表示の方法については具体的に規定しておらず、単に「意思表示」とされています。
したがって、明確な返事をせず無言でいた場合でも、契約が成立したと見なされることがあります。
これを「黙示の承認(または承諾、契約)」と呼びます。
「明確に返答していないのに、なぜ承諾したと見なされるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
先述のとおり、民法では意思表示の方法について具体的な規定がありません。したがって、文書、口頭、態度(頷く、首を捻る、黙認する)など、いかなる方法であっても、意思の存在を推測させるに足る外形的行為があれば、それが意思表示とみなされる可能性があるのです。
たとえば、賃貸住宅や借地の賃借人が、第三者に転貸(又貸し)していることを賃貸人が知りながら、それを黙認して家賃や地代を受け取り続けた場合、それにより「転貸を承諾していた」と見なされることがあります。
その場合、物件を占有している第三者に明け渡しを求めても、「黙示の承認によって転貸が承諾されており、自分にはすでに賃借権が成立している。したがって、何らの立退き条件も示されていない状態では応じるつもりはない」と反論されるかも知れません。
もっとも、私たち不動産業者は宅地建物取引業法の定めに基づき、法34条の2(媒介契約)、法35条(重要事項説明書)、法37条(売買契約書)など、契約に関する書面についての作成が義務付けられています。
したがって、本来であれば不動産取引において黙示の承認を巡る争いは起こりにくいはずですが、実際にはそのような争いが多発しています。
今回は、黙示の意思表示によるトラブルを未然に回避するため、どのような場合に容認され、また否定されるかについて、裁判例を参考に解説します。
売主が直接売買したことにより請求した損害賠償が否定された事例
まず、令和3年12月に東京地裁で争われた裁判例を見ていきましょう。この事件は、媒介業者(原告X)による折込広告を見た顧客(被告Y・個人)が、複数回の内覧を経て購入意志を示し、購入申込書の提出と同時に売買契約の締結予定日を定めました。これにより原告Xは、融資申込みの代行や売主との減額交渉、売買契約書等の作成などの履行に着手します。
ところがYは、そこまで話が進んでいるのにもかかわらず他の媒介業者(B)に自ら連絡し、本物件の媒介を依頼すると同時に、Xに対し購入意志の撤回を連絡します。
その後Xは、本物件の売主(A)からBの媒介により契約締結の準備が進められていることを教えられます。Xは相応の履行に着手していたのですから黙ってはいられません。Yに対し、自社の媒介で契約を締結するよう求めます。
媒介業者(B)は経緯を知らず契約準備を進めていましたが、YとBが争っているのを耳にして媒介業務を取りやめます。道義的に考えてもYの行動は容認されませんから、身を引くのは妥当な判断でしょう。

それによりYが、Xに再度依頼して契約していれば問題も生じなかったのでしょうが、媒介業者を介入させずAと直接、売買契約を締結してしまうのです。
この場合、遅くとも購入の意思表示が示された時点までに、媒介業者XとYとの間で媒介契約が締結されていれば、例え直接契約がなされても約定報酬額に相当する金額を違約金として請求できたでしょう。しかし、媒介業者Xはそれを怠っていました。
ですが、複数回の内見に立会ったばかりか、価格交渉や融資申込みの代理、契約書等の作成などの役務は提供しています。
そこで媒介業者Xは、「媒介契約が成立していなかったとしても、媒介報酬の期待を侵害した、若しくは媒介報酬を得ることが確実であるとの期待を侵害しないよう務める信義則上の義務を怠ったことは違法である」と主張し、媒介報酬相当額を損害賠償金として求め訴訟を提起したのです。
訴えに対しYは、「媒介契約が締結されていない以上、契約は成立していない」、「Xが主張する、黙示の承諾を裏付ける根拠とした一連の業務は、媒介業者として契約の成立に向けて無償で行うべきものであり、根拠にはなりえない」と反論します。
訴えにたいし裁判所は、「不動産の媒介契約は、不要式の諾成契約(当事者間の合意によってのみ成立し、特別な方式が要件とされない)である」として、黙示の承諾であっても成立しうるとしながらも、「一般の購入者にとって、媒介報酬は高額に上るものであり、契約締結には慎重な判断を伴うとはいえ、通常、媒介契約書の作成なくして契約が成立し得るとする意志を有しているとは考え難い」と判事します。
同時に、宅地建物取引業法で媒介契約締結後の遅滞なく所定の事項を記載した書面を交付することが義務付けられていることに言及し、媒介業者Xが主張する黙示の承諾(契約)が成立しているとすれば、それにより宅地建物取引業法に違反することになりかねないとしました。
さらに追加で判事された以下のようなポイントを、私たちは理解しておく必要があります。
●媒介契約は、売買契約が成立した時に報酬を請求しうるとしており、契約が成立されるまでは、それまで遂行した業務については媒介報酬を生じる役務とは見なされない。
●媒介契約成立への期待は抽象的概念であり、法的保護に値する権利ではない。
●申込み書の提出があっても、それにより売買契約の締結が義務付けられるわけではない。
これらの判断により、媒介業者Xには損害賠償請求が認められませんでした。
判決を不服として媒介業者Xは東京高裁に控訴しますが、控訴審で裁判所は「契約が口頭で成立するには、契約における重要な要素について双方の意思表示が合致していることが必要だが、本件において媒介報酬額の合意成立は認められないし、媒介契約の有効期間や違約金等についても説明が行われず合意されていない。したがって、媒介契約は成立していない」として請求を棄却しました。
不動産業者である私たちは、被告Aによる一連の行動や主張は、何とも腹立たしい印象を受けます。しかし実務上、私たちが提供した情報に基づき直接契約する、所謂「抜き行為」は数多く確認されます。それを法的に防止する意味でも、媒介契約の締結は必須なのです。
購入希望者との媒介契約締結については、そのタイミングについて様々な見解もありますが、可能な限り速やかに、遅くとも購入の意思表示が示されるまでに締結しておく必要があるのです。
媒介報酬の請求が、一部認められた事例
裁判例では、黙示の媒介契約の成立を認めた事例もあります。平成27年3月に東京地裁で出された判決がそれです。
まずは事件の概要を見ていきましょう。
買主Y(被告・一般事業法人)は、媒介業者X(原告)の媒介により、Yが所有する物件の隣地2物件(A所有物件24億円、B所有物件22億4100万円)を買い受ける売買契約を締結しました。
売買契約の約定として、売主は引渡し期日までに売買の目的を阻害する一切の権利を解除、排除する旨を定めていましたが、実際には賃借人を退去させることができず、そのため売買契約の特約に基づき、A所有物件を19億2000万円、B所有物件を17億9280万円に減額し、その額で決済・引渡が行われました。
そこで媒介業者Xは、当初の売買契約締結金額に基づいて媒介報酬を請求しました。
媒介報酬は原則として、売買契約締結時に全額を請求できます。しかし実際には、契約時と決済時の2回に分けて請求するのが一般的で、決済時に請求するケースも珍しくはありません。
ところが買主Yは、「媒介業者であるXは、当社にたいし物件の売込をしてきたに過ぎず、当社としては自社の関連会社である宅建業者Cに媒介を依頼しており、Xには媒介を依頼していない」として支払いを拒みました。このケースでも、媒介業者Xは買主Yとの媒介契約締結を怠っていたのです。
ただし、前回の事例と異なり、媒介業者Xが作成した売買契約書により契約が締結され、決済も完了しています。
裁判所は、媒介報酬の支払いを求めて提訴した媒介業者Xによる主張を一部容認しました。
まず、売買契約が締結されるまでにXの間には、「報酬額について定めのない黙示の媒介契約が成立していたものと認められる」と判事しました。
その理由として以下の点が挙げられています。
●売買契約書には媒介業者Xによる記名・押印があり、さらに特約条項にも「本物件の媒介業者である株式会社X」との記載がある。しかし、Xが売主側の媒介業者であると限定する記載はない。
●媒介業者Xは、Yに対し重要事項説明の交付および説明を行っており、同説明書にも宅建業者としてXが記載され、取引態様も売買の媒介とされている。
●決済・引渡に関する概要もXからYにたいし伝えられており、さらに引渡をもって媒介業務を完了する旨が通知されている。
Yによる「媒介は関連会社であるCに依頼しており、Xは物件を売込にきたに過ぎない」との主張に対して、裁判所は「確かに、本件不動産売買契約書の媒介人の欄には、媒介業者Xの他に、媒介業者Cの記名押印があり、YとCとの間で一般媒介契約書が作成されている」と、外形的な要件の存在を認めました。しかし実態として、「本物件成約に向け、CがAやBと接触して媒介行為をした形跡はない」としたのです。

Yは、「媒介報酬が1億4千万円弱に達するような場合に、その額や支払時期等の明細について、何ら契約書(媒介契約書を指しています)が存在しないことは常識的にあり得ない」と反論しました。
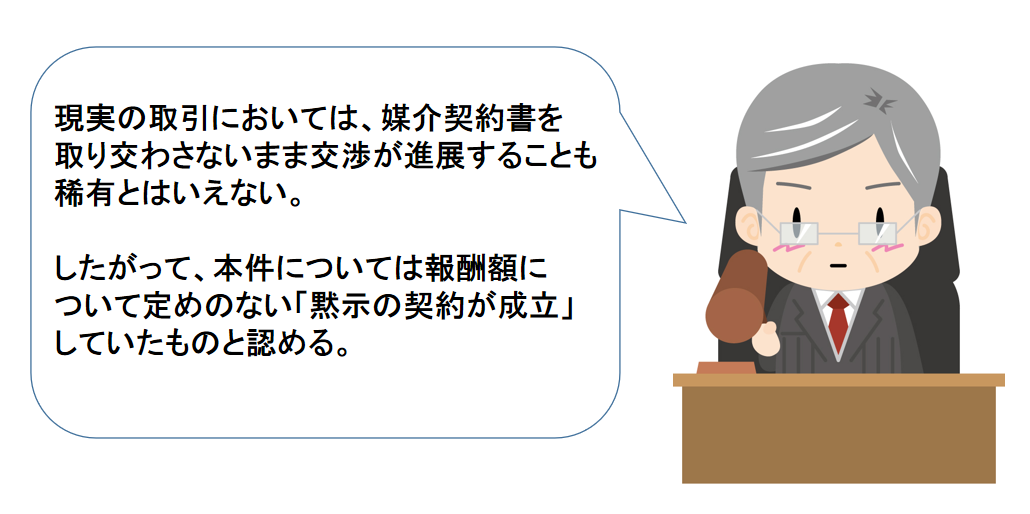
それを受け裁判所は、「不動産の媒介契約は諾成・不要式の契約である上、不動産の媒介報酬に関する異次の裁判例が示すように、現実の取引においては、媒介報酬が高額に及ぶ場合であっても、媒介契約書を取り交わさないまま交渉が進展することも稀有なことではなく、その主張は採用できない」と退けました。
この裁判では、Xが遂行した一連の業務により「黙示の契約」があったと認められたのです。しかし、媒介報酬については、売買金額減額後の正規報酬を基準に、その60%(約7024万円)が報酬とされました。
まとめ
令和3年12月の裁判例では、「媒介契約書の作成なくして契約が成立し得るとする意志を有しているとは考え難い」と判事し、媒介契約の締結がないまま契約準備に入ることはあり得ないとしました。しかし、平成27年3月の裁判例では「現実の取引においては、媒介契約書を取り交わさないまま交渉が進展することも稀有なことではい」と判事しています。
いずれの裁判例でも、「媒介契約は諾成・不要式の契約である」としています。つまり、「売りたい」、「購入したい」などの意思表示が口頭もしくは黙示、つまり行動や態度、周囲の事情等などから総合的に判断される場合には、媒介契約が締結されたとみなされる余地があるとしているのです。
ただし、これはあくまで民法による判断基準の一例に過ぎません。
どちらの裁判例でも、あらかじめ依頼者と媒介契約を締結していれば、トラブルは回避できたでしょう。問題は、媒介の委託が曖昧なまま業務を遂行した点にあります。
宅地建物取引業法第34条の二では、媒介契約を締結した際には、遅滞なく所定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付することを義務付けています。
実務上、購入検討者に対し、どの時点で媒介契約を締結してもらうか判断に迷うところもありますが、少なくとも媒介契約を締結しないまま売買契約を締結することは避けるべきなのです。