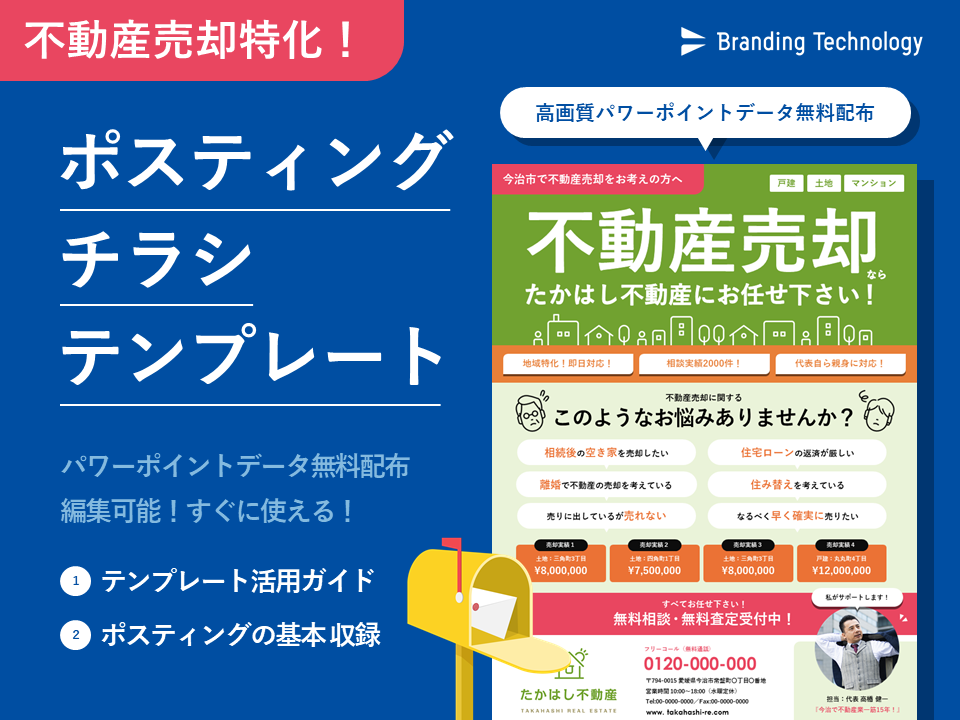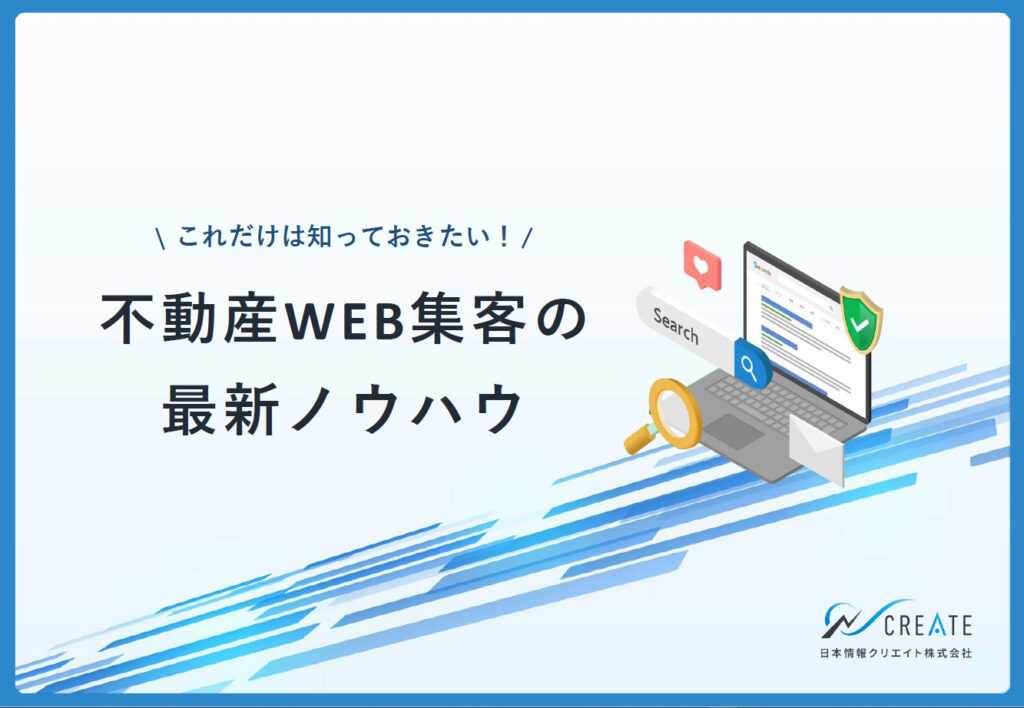リテラシーとは、特定の分野に関する知識や理解力、そしてそれを活用する能力を指す言葉です。
本来は「読み書きをする能力」を意味しましたが、現代においては情報リテラシー、ITリテラシー、メディアリテラシーなど、多岐に渡る領域でその重要性が認識されています。
IT技術の飛躍的な進化に伴い、活字文化のあり方は変化し、不動産の広告戦略も大きく様変わりしました。
これまでの折込チラシに代わり、ホームページやSNSが主流となり、手軽かつ低コストで情報を発信できるこれらのツールの積極的な活用は、もはや不可欠となっています。
しかしながら、不動産業者の公式アカウントで不適切な情報を発信した場合、瞬時に炎上を招き、企業のブランドイメージを著しく損なうだけでなく、事業活動そのものに支障をきたす深刻な事態に発展する可能性があります。
それは公式アカウントに限った話ではありません。
時に、従業員が個人的に利用するプライベートアカウントからの個人情報漏洩が炎上につながった事例も散見されます。
2016年に発生した、不動産媒介業者に勤務する女性社員が、店舗に来店した芸能人夫婦についてX(旧Twitter)に書き込んだために炎上したケースは、その典型的な事例と言えるでしょう。
また、あるハウスメーカーでは、展示場を訪れた顧客が階段下のビスの不備を投稿したことに対し、投稿者宅を訪問して削除を要請し、さらには法的措置を検討すると発表したことで、「スラップ訴訟ではないか」との批判を受け炎上した事例もあります。
これらの問題が発生する原因は多岐にわたりますが、その根本には「リテラシーの欠如」というよりも、「モラルと倫理の欠如」があると考えられます。
不動産業者に限らず、これまでも全ての事業者にモラルと倫理は求められてきました。
しかし、情報発信が容易となったことで、これまで以上に強く求められるようになったのです。
モラルと倫理は、ともに社会における行動規範を指す言葉ですが、モラルが個人や家族といった比較的小規模な集団における道徳的規範や価値観を示すのに対し、倫理は社会全体にわたるより広範な規範やルールを指します。
企業としての信頼を築き、持続可能な事業運営を行うためには、単に情報発信の技術的な側面である「リテラシー」だけを高めるだけでなく、その根底にある「モラル」と「倫理」という、人としての根本的な規範を従業員一人ひとりが深く理解し、実践することが求められるのです。
本稿では、従業員のプライベートアカウントから顧客の個人情報漏洩が確認されたことを根拠に、社員を「懲戒免職できるか」との相談事例を始めとして、企業に求められる対策について詳細に検証します。
SNSの利用制限は合法か
不動産業界の特有な傾向かも知れませんが、従業員によるSNS投稿での炎上を懸念し、その利用を全面的に制限することを考える経営者によく遭遇します。
これは、従業者10名以下の企業が全体の9割以上を占める当業界ならではの思考かも知れません。
しかしながら、このような包括的な利用制限は、労働者の私生活に対する不当な介入とみなされ、違法行為と評価される可能性があります。
また、SNSへの個人的な投稿を重ねることでファンを醸成し、顕著な成果を挙げている従業員も少なくありません。
そのため、戦略的なマーケティング活動を阻害する全面的な禁止は、合理的な経営判断とは言えないのです。
一方で、従業員のプライベートアカウントへの投稿が企業に不利益をもたらす可能性は確かに存在します。
したがって、下記のような具体的なルールを設けて制限することは許容されるべきです。
- 従業者や役員の個人情報に関する投稿
- 企業の機密情報や顧客の個人情報に関する投稿
- 著作権や肖像権など、第三者の権利を侵害する内容の投稿
- 業務時間中のプライベートアカウントへの投稿
- 同業他社を根拠なく批判する内容の投稿
- 遵法精神に欠ける内容、あるいは誤った法解釈などを解説する投稿
- 社会人としてのモラルが疑われる内容や表現による投稿
これらは一例ですが、いずれも勤務先である企業の評価に影響を与えうる投稿です。
「この程度のことは常識で皆理解しているだろうから、わざわざルールを明文化する必要はない」と考える経営者も少なくありません。
しかし、SNSの高い拡散力を考慮すると、炎上してから慌てて削除しても手遅れであることが大半です。
知事選挙の広報を任されたと投稿して炎上したPR会社の代表も、プライベートアカウントへの投稿だから問題ないという安易な認識が招いた結果かもしれません。
それでは、プライベートアカウントへの投稿が炎上したことを理由に、従業員を処分できるのでしょうか。
この判断は、就業規則やルールの明文化の有無、定期的な指導や研修の実施状況などが総合的に勘案され、適法か否かが決定されます。
処分の適法性を巡る裁判は多数確認されますが、現状では一貫した判断基準が確立されているとは言い難い状況です。
したがって、従業員への処分を検討するよりも、まずは炎上を未然に防ぐ体制づくりを講じるのが賢明なアプローチです。
具体的なガイドラインやルールの策定、定期的な社員研修、そして企業全体のモラルと倫理観の醸成こそが、不動産業界におけるSNSリスクマネジメントの真髄と言えるのです。
危機管理体制の構築
即時性・匿名性・公開性という特質を持つSNSは、個々人が瞬時に自己の見解を不特定多数に表明できるシステムとして発展しました。
しかし、これらの特性ゆえに、その表現内容によっては他者の人格権(名誉・プライバシーなど)を容易に侵害し、さらには特定個人だけではなく、民族・人種・特定の団体などを名指しした攻撃的なヘイト言論や増悪表現を展開する温床ともなっています。
近年ではさらに、巧妙なフェイク動画や誤情報が、世論を意図的に誘導する目的で発信されている事例も多く見られるようになりました。
表現の自由は日本国憲法第21条第1項で規定された国民の権利であるため、これを一方的に抑圧することは言論統制に当たる可能性を否定できません。
この判断基準については、法曹実務者の間においても意見が別れており、実際、最高裁判決を筆頭に各種裁判例を見ても、未だ明確な基準が確立されているとは言い難い状況です。
それでは、企業は従業員がプライベートアカウントで業務や顧客情報、会社の機密情報などを公開していないか、その内容を閲覧する権利はあるのでしょうか。
「表現の自由が保証されているのだから、応じる必要はない」と対抗されれば、企業は法的手段を講じずその開示を強制することはできません。
企業は一定の監視権限を持つべきてあるという立場がある一方で、一方的な監視が法的に許される範囲を超える場合もあるからです。
しかしながら、表現の自由は無制限に保証されているわけではありません。
最高裁判所は平成5年3月16日の判決において、「表現の自由は、公共の福祉による合理的でやむを得ない程度の制限を受けることがあり、その制限が容認されるかどうかは、制限が必要とされる程度と、制限される内容及び性質、これに加えられる具体的制限の態様及び程度などを較量して決せられるべきである」との判断を示しています。
さらに、基本的人権の享有に関する保持と責任を規定した日本国憲法第12条では、その後半部分において基本的人権の濫用を禁止し、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされています。
つまり、私人であっても無制限に表現の自由が認められているわけではなく、仮に投稿した内容が公共の福祉に反し、企業に損害を与えるものである場合には、一定の制限が受けてもやむを得ないとも考えられるのです。
ですが、現行法において明確な判断基準が設けられていない以上、企業が法的な手段によらず、プライベートアカウントから発信された内容の開示を強制することは困難であることを理解する必要があります。
そのため、SNSによる炎上を防止するためには、従業員に対して表現の自由に関する啓蒙教育を実施すると同時に、企業SNSの投稿ルールはもちろんのこと、プライベートのSNS使用に関しても推奨マニュアルを策定し注意喚起する必要があるのです。
誤字や脱字などのヒューマンエラーも含め、誤解を与えかねない不適切な表現の投稿を防止するためには、公式SNSアカウントへの投稿についてはチェック機能を持たせる必要がありますし、万が一の炎上に備え、対応マニュアルを策定しておくことも重要です。
企業規模が小さいからそんな手間をかける必要はないと考える経営者は多いのですが、規模によらず不特定多数に対して情報を発信することを可能にしたのがSNSというネットワークシステムであることを忘れてはなりません。
心無い不適切な投稿が、企業の信頼を損なう原因となる可能性があることを認識する必要があるのです。
まとめ
SNSによる不適切な発言が、公職者の辞任問題まで発展する事例は後を絶ちません。
文章で自身の意図を正確に伝達することは、文筆を生業にするプロでさえ至難の業です。
ましてや文字数制限のあるSNSでは、意図せず投稿した内容が炎上する可能性は格段に高まります。
もちろん、リスクを避けるためにSNSを利用しないという選択肢はあります。
しかし、手軽に情報を発信し、顧客獲得にも期待できるSNSの利用を放棄することは、収益性の観点からみても賢明な策とは言えません。
投稿内容が読者にどのような見解を抱かせるか慮る気持ち、そして人には多様な価値観が存在することを理解していれば、問題は生じにくいかも知れません。
しかし、これらは個人のモラルと価値観に大きく左右されるため、画一的な正解は存在しません。
このような状況下において企業に求められるのは、法的基準が未だに確立されていない現状を認識した上で、社会通念上問題がない範囲内で従業員への啓蒙教育に努めることです。
加えて、SNS利用に関する明確な社内ルールの策定と、万が一の事態に備えた危機対応マニュアルの整備が、企業が講じるべき「防衛手段」となります。
変動する情報社会の中で不動産事業者が持続的に成長を続けるためには、SNSを積極的に利用する「攻め」の姿勢と、予期せぬリスクから企業を守る「守り」の体制、この両輪が不可欠なのです。